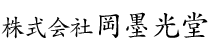2020年6月号:第2回 裂の復元の始まり(2)
岡 興造(談)
〇構造から復元する意味
前回お話したように、必要に応じて取り組んできたことが墨光堂の復元の始まりです。金襴や、次回お話する錦、綾を織組織まで含めて復元した経験から、文様を形としてだけ見る場合と、構造から起こしていく場合とのできあがりの違いを知りました。特に、前回お話した「関山号」の金襴は、すべての条件が揃ってなしえることができました。現物(本手)を参照できたこと、文図の作成に拡大写真を利用したこと、糸目をひとつずつ拾っていく時間があったこと、専門家のアドバイスが受けられたこと、専用の機(はた)を立てることができたこと、そしてそれにかかわる人々の協力、これらの条件をすべてクリアすることは、現在ではなかなか難しいように思います。
裂によって一文様の経糸の数や釜巾は違い、三釜、四釜、五釜など釜巾の経糸の数を釜数にかけたものが織巾の糸数となります。復元はこの経糸の数を知ることから始まります。しかし現在では、文様に合わせた機作りには予算が多くかかることや、一回ずつ機を立て経糸を直すといった手間がかかること、それに対する費用が直接裂地代金にはねかえってくることから、よく使用されている織機に文様を合わせることが多くなっています。機に合わせると文様の微妙な部分が表現できなくなってしまうことになりますが、昭和が終わり、平成、令和となり、修理の進め方や方向性、内容、予算が変わってきました。機を立てれば、復元の予算は5倍から10倍に膨らみますし、一つの文様の裂地を作るためには、ひと経(たて)10反は織る必要があります。一つの復元のために、一文様の織物を多く作ることになり、多くの在庫を持つことになります。掛軸の表装に用いる裂地の量は知れています。10反分を使用するにはいったいどれだけの時間がかかるでしょうか。復元をするごとに在庫をもつことは、長い目でみれば、その後の取り合わせの選択肢を増やすことにつながります。しかし、一事業単位で予算や内容を考えれば、なかなか構造から復元することはできず、文様が少し変わることには目をつぶり、ひと経で複数の文様を織ってもらうような発注をするようになってしまっています。
また、時代によって作業効率が考えられ、織の構造が変わってきたということもあります。例えば、金襴の地搦み裂であれば裏面に金糸が浮いて出ます。浮いた金糸は、軸装にする際の裏打ちの作業のときに、裏梳きと呼ばれる裏面処置を行います。この手間がかからないように、近年では袋織などを変えて全て綴じ込めて一体化するように織る工夫がなされています。軸装にする際の手間を省き、仕事の効率がよくなるように工夫され、すべてがこのような織になってしまっているといっていいほどです。文様は同じだと言いますが、例えば地搦みならば地が平滑で文様がしっかり際立つことや、袋地ならば文様と地の差でやわらかな表現が見えることなど、織構造が支える裂の持ち味、表情というべきものが犠牲になってしまっています。古書画と現代作家の表装では、内容や表現によって合わせ方が変わりますが、古書画の表装では、中世の表装の美意識が完成した時代の裂地が基本となっており、本紙との取り合わせなどの美意識から生まれたものであるということを忘れてはならないと思っています。
〇綸子の危機
中国で表装裂(総縁)に使われていた綸子も、作業性にあわせて織組織が変えられた例としてあげられます。綸子は、極細の生糸で撚りをかけずに織り上げた繻子地の織物で、その後、練り、染めという工程で仕上げます。中国では仕上げに砧打ちをしていたと言われています。1984年に南京の雲錦研究所を訪れた際、石の上に折りたたんだ綸子を置いて砧打ちをしていた写真を見ることができました。今でもよく覚えていますが、20年後に研究所を再訪したときにはこの写真を見ることができませんでした。何かの機会にもう一度このことを調べてみたいと思っています。
文化大革命前まで織られていた綸子は繻子地でしたが、その後、繻子地は織の工程で多くの加工が必要であることや、取り扱いが難しいこと、裂地がよれたりよく手にひっかかったりするなどの理由から、使用するときに便利な綾織に織組織を変えて織るようになったようです。綾織で練糸を使用すると、糸に縒りがかかっています。こうすることで先染の光沢のある織物になります。時代の要求もあり、現場の技術者からは、厚みが増されて取り扱いがよくなったという声が上がっているとも聞きました。
明代や清代の表装の軸物や巻物に使われている綸子には、繻子地の薄物の持っている美しさがあります。しかし現代は綾織であるため、しなやかなシャープ感がなくなっています。残念なことに、今日では本来の綸子を織る技術はなくなっているそうです。ほんの50年間の間に変わってしまいました。現在工房に残っている未使用の綸子の裂地を大切に使用しなくてはならないと思っています。この綸子の話は他人事でありません。技術は必要とされなくなればすぐに消えてしまいます。日本でも同じように、本来の美しさをもったものが求められなくなり、作らなくなることによって、技術が途絶えてしまうのではないかと危惧しています。
〇西陣の現在、日本での課題
昭和40・50年代には西陣が活況を呈していました。平成に入ると織物の世界は生産・販売量が大きく減少していきましたが、廣瀬敏雄氏の跡を継がれた廣瀬賢治氏に周囲の人々の協力を取り付けてもらい、力を合わせて今までの発注方法を変えていきました。裂地問屋に発注するのではなく、文様や組織、糸使いなどを織屋さんと細かく決めて作る方法が、賢治氏の理解・協力で可能になりました。金襴、錦、綾のほか、緞子や後染用無地裂(上下用)、羅についても、廣瀬氏の協力を得て高度な裂地を作ることができました。また、これについては別にお話の機会を持ちますが、絵絹(劣化用)の復元も忘れてはなりません。廣瀬賢治氏は2017年に他界されました。次の世代に裂の価値観を伝えていくためにも、氏の協力を得て調べたいことや試したいこと、話し合っておきたいことがいくつもありました。そうして次の年代になっていくことは世の中の常とはいえ、同齢の私には急な別れが無念であり、あと少しの時間がほしかったという思いが強くあります。現在は子息が跡を継がれています。賢治氏が残された技術等を継承していい織物を織ってほしいと願っています。私自身、ものの価値観や考え方、知識、工房の個性をどう伝えていくか、自分の役目としてどう受け止めていくかを考えています。
織屋さんの世界も時代をおって段々厳しくなっています。分業化が進んでいる西陣織の世界では、簡便な機械化が進み、手織の柔らかさや風合が必要とされる発注が少なくなってしまいました。また、この半世紀で、畳、襖の生活がなくなりつつあり、特に床の間が生活空間から消えてそこにかざる軸物が必要とされなくなるなど生活環境が大きく変わりました。手織の柔らかさや風合のこだわりも時代の流れで表面的なものになり、価値観の違いが大きく見られる時代になってしまったのではないかと感じます。中国の綸子の例のように、ものの見方、感性が一度失われれば、これを元に戻すことは容易ではありません。繰り返しになりますが、古書画の修理時に使用されている中世以来の織物に対する価値観を共有し、裂地の復元が高度に達成されるためには、専門家との協力をはじめさまざまな条件が整わなければなりません。その技術や材料、道具が危機的状況にあること、それに伴って知識や眼力、美意識が失われつつあることに大きな危惧を抱いております。
裂の復元を例にとれば、予算や織の現物の条件が整えば行うことができます。そして、復元を行うことによって、失われつつある技術を残すことができます。文化財の修理をする行為は、100年に一度の後世へ伝えていく機会でもあります。国宝などの文化財の裂地を新調するとなれば、現場としては、すべての条件を整え、作品が生まれた時代を考え、よりよい裂地をつけることを望むのが当然ではないでしょうか。しかし、現実には、修理する作品が多くあるなか、予算など総合的に考えると、裂へのこだわりの重要性を選択する難しさがあります。
文化財修理の、本紙を修理する技術やそれに対する材料の開発は、多くの面で脚光を浴びます。しかし、東洋の文化財の形の中の一つの軸装は本紙と表装裂が一体となっており、そのすべてを大きな流れの中で次に受け継いでいくべきものです。表面的に見えているものを支えているのは、それを使用している技術者であり、また、依頼者の仕上がりへの要求の高さです。これは現場に立っている技術者の大きな課題として肝に銘じなければならないと、近年特に思います。
(第3回に続く)