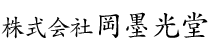2024年1月号:第19回 日本の文化財修理における“地色補彩”について(6)
亀井 亮子
○第3章 イタリアにおける文化財修復と補彩の歴史
第5節 比較- “中間色補彩”と“地色補彩”
ここまでの内容をふまえて、日本においての地色補彩と欧米においての中間色補彩を改めて比較してみることとする。
先ず時期についてであるが、日本で地色による補彩が実際に行われ始めたのは1970年代である。それに対してイタリアにおいて中間色による補彩が考え出され使われていたのは地色補彩に先行する1940年~70年頃になる。完全に同時とはいかないまでも、両方の方法が存在する時期は非常に近いといえる。そしてこれは、修理修復を行っている人々の間で“いままでのようなやり方ではいけないのではないか”という風潮が強まっていたのではないかということとも捉えられる。
次にこれらの技法の視覚的な特徴について述べる。当然絵画の材質や手法も、補彩を行う時に使用する画材も異なるので、全く同じというわけにはいかないことを承知した上で比較してみる。どちらの技法でも、画面に存在する欠失箇所に1つのベースとなる色を定めて、欠失の周囲に合わせることなく塗るという手法を採っており、それが2つをよく似ているもののように見せている。しかし内容をより詳しく見ていくと、中間色補彩が「灰と緑の混合色、栗褐色、暗褐色などと色彩改変を重ね、数多くのパターンをもつに至る」1というように、多くの、しかし決められた色の中から選んだものを色面に塗っていくのに対し、地色補彩は第2章でも述べたように、かなり柔軟な考え方を基に、絵画面の中で臨機応変に使用されている。
そして、それぞれの手法を成立させるにあたっての考案者側の思惑であるが、まずそれまでの周りに合わせる補彩に対して、否定的な方向から始められたという点では似た状況であると言える。しかしチェーザレ・ブランディによって行われた中間色補彩は、鑑賞者の想像が介入する余地を除くために行われたものであるのに対して、日本の地色補彩は、鑑賞者の想像を喚起し、その想像力に委ねるという効果を考えて施されたものであった。つまり、視覚的には似ているように見える技法であるが、全く逆の効果を狙って行われたということになる。更に、中間色補彩のこだわりが“欠失箇所の存在を目立たせない(絵の有る位置から奥へ押し戻す)”というところにあったのに対し、地色補彩は徹底的に“絵を見せる”というところに重きを置いていた、と言えるのではないだろうか。また、中間色補彩とは、ブランディが「めぐりあえない時間」と表現し、田口かおり氏が「異なる時間性の交錯」2と解釈するように、目に見えない“時”を表現しようとしたものであったのに対し、地色補彩は、絵画面のマチエール(質感)の表現など“見せ方”にこだわり、そこを表現しようとしているものであると言える。
つまり2つの技法の本質として、“中間色補彩”は理論を中心に構築されている要素がかなり大きいということに対し、日本の“地色補彩”は感覚的な要素が大きいと共に、徹底的に物に則して考えられていると言い切ってしまっても言い過ぎではない。この場合の“物”とは、絵画であり、材質でもある。つまり見方によっては、2つの補彩方法は似ているようで、実は全く異なるものであると言えるのである。
おわりに
第3章でも述べたように、イタリアにおいてチェーザレ・ブランディが率いる国立機関が単独で、率先して始めたようなものであったという“中間色補彩”は非常に短い期間で姿を消している。田口氏によると、それまで他のどの機関や研究者も補彩について理論的に説明した前例は無かった3ということであり、その新しさが一時多くの人を、研究や批判を含めて引きつけたと考えられる。「著名な重要作品に関して「オリジナルの領域を守る」ということを徹底的にやった」4結果でもあった中間色補彩であるが、その根幹である理論を突き詰めていくに従い、意図するところとの齟齬が生まれていく。そしてついにはその技法を考え絵画の補彩に使うことを始めたブランディ自身が「そもそも中間色というものは存在しない」5という否定的な言葉を残すに至っている。
対して日本の修理における“地色補彩”は、考案されてから40年以上経った今も尚、指定文化財の補彩における「原則」として存在し続けている。そこには、技法を考え実現した中に修理の方向を“指導する立場”にある人物が深く関わっていたということも、要因の1つとして挙げられるであろう6。岡興造氏によると、渡邊明義氏の絵画修理や補彩に関する考え方については終始一貫されており、一度として変わることは無かったという。しかし、それだけではこのように長く1つの技法が使われ続ける理由にはならない。岡泰央氏が述べているように、「絵画の表現や材料に由来して」、「我が国の絵画表現に地色補彩というものが非常に適している」7といったこともまた大きな要素として挙げられる。そして最大の理由としては、やはり日本の修理においての“地色補彩”に対する考えの柔軟さが挙げられるのではないか。“中間色補彩”では欠点として挙げられた多様性8が、“地色補彩”においては長所として重宝されているように思われる。
その性質からも予想できるように、第2章で取り上げた1970年代の“地色補彩”と、現在使われているそれは、様々な点において必ずしも全く同じではない。重要文化財『両界曼荼羅図(敷曼荼羅)』(教王護国寺所蔵)や国宝『仏涅槃図(応徳涅槃図)』(金剛峯寺所蔵)の修理以後も多くの補彩事例が存在したが、“地色補彩”はそれぞれに柔軟に対応する幅を持った技法として技術者に引き継がれ、補彩の「原則」として現在も使用され続けているのである。
しかし、現在、日本においての地色補彩については、長く使われ続けてきたが故の弊害も多少あるのではないかと考える。近年、日本においても修理の技術や方法論は徐々に整えられて後進へと伝えられ、学ばれるようになった。補彩についても同様である。その中で、時にこの原則としての“地色補彩”という言葉自体に、言うなれば囚われてしまっているのではないかと思われることが、少なからず見受けられるのも事実である。例えば、補彩を行う際に“まずこの絵画の地色は何か”という話が出ることがよくあるが、それに終始囚われすぎると、場合によっては補彩と絵画の間で理屈に合わない部分が出てくるということが往々にしてある。そのようなことから見ても、“地色”を第一に考えるというより、そこに重心を置きつつ、修理の対象となる絵画自体が、補彩という工程を経ることでどのように見えるようになるのか、どのように見せることができるのかということを第一に考えることこそが大切なのではないかと考える。
度々議論がなされていながら未だ行きつ戻りつしている欧米の例を見ても明白なように、価値観や基準とは常に移ろうものであり、万人が納得する明確な答えというものは無いのかもしれない。しかし今、再びこの“地色補彩”という方法が使われるに至った経緯を知り、その本質を見なおすことにより、つまり“地色補彩”とは、あくまで手段の1つであり、目的ではないということを踏まえ、この責任ある修理工程について改めて考えることができれば、この工程への向き合い方に深みが増すのではないだろうか。
(日本の文化財修理における“地色補彩”について 了)
《註》
1 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.93~94
2 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.100
3・4 田口かおり氏へのメールでの取材に対するコメントによる。
5 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.101
6 株式会社松鶴堂に所属されていた樋口光男氏によると、昭和40年代半ば頃から宇佐美松鶴堂で指定文化財の補彩を担当されていた徳永敏氏は、渡邊明義氏の紹介で入社されたということである。徳永氏は渡邊氏の意向をよく理解されており、“地色補彩”についてもどのようなものであるかをよく語っておられたという。1970年代当時、徳永氏は異なる工房間で作業をされていたこともあったらしく、国宝『伴大納言絵詞』(出光美術館所蔵)の補彩を担当された田畔徳一氏は、徳永氏から補彩の手ほどきをうけられたということである。このようにして、渡邊氏が中心となって進められた“地色補彩”は、氏が直接指導されたり、氏の意向を理解している人物が他に教え広めるという形で徐々に認知され、やがてその方法は指定文化財の修理を行う際に持つべき基本的な考え(倫理観)として広がり浸透していくこととなる。
7 岡泰央「翻訳者によるあとがき」ティナ・グレッテ・プールソン『修復は紡ぎだす詩』三好企画、2014年、p.190~191
8 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.102