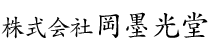2022年12月号:第16回 日本の文化財修理における“地色補彩”について(3)
亀井 亮子
○第2章 戦後日本における文化財絵画の修理―近代的“補彩”の成立
第4節 日本における“地色補彩”の定義-その後
現在、国宝や重要文化財のような国指定文化財における修理報告書等で、修理の工程の一つである補彩の欄には、“地色を基調とする補彩を行う”という表現が用いられることが多い。“地色”自体は広辞苑にも掲載されている言葉であり、特殊なものではないが、“地色補彩”という言葉は、修理の現場で作られた造語1である。現在では公式の出版物、例えば国立博物館が発行している報告書集にもその記述が見られる2ことから、補彩の方法を表す言葉として公に認められていると考える。
具体的に“地色補彩”とは、渡邊明義氏の言葉を借りるなら、「(作品の)色の中から標準的な色を見定めて決められた色」3を主に使用して絵画の欠失部分に繕われた補修紙、補修絹に色を塗る(補彩を施す)という方法である。前述(web修復第15回)の国宝『伴大納言絵詞』(出光美術館所蔵)の修理の際に取り入れられたこの補彩方法は、やがて指定文化財の欠失部分に施す彩色の基本的な考え方とされていく。しかし、全てが同じ扱いや考え方でまとめられるほど、補彩は単純なものではないのも事実である。そのような問題の一つとして、作品の性質によって補彩の扱いが異なるケースがある。前述の具体例は2作品とも紙本の絵巻であるが、作品の種類や形式によっては、また異なった問題を伴う場合がある。
1970年(昭和45年)から修理が行われた重要文化財『両界曼荼羅図(敷曼荼羅)』(教王護国寺所蔵)(東寺展パンフレット参照)の補彩において、地色補彩は新たな問題に直面することになる。この作品は、仏画の補彩における転換点であったと当時作品の修理に携わった岡興造氏は述べている。渡邊氏も、本作品の補彩を「観念を優先させて決断した例」4であるとしている。しかし、それらは決して簡単なものではなかったようである。当時、修理の現場では実際にどのようなことが起こっていたのだろうか。
『両界曼荼羅図(敷曼荼羅)』の修理は当時の担当工房によって着々と行われ、補彩も大分進んだ頃に渡邊氏が見に来られた。しかし、補彩の施された敷曼荼羅を見て、一言「違う」と言われたという。そのことは渡邊氏も後に回顧文で「始まっていた補彩の作業を止めてやり直しをさせた」と記されており、氏はそれを「苦い決断であった」と振り返っている5。では何が違ったのだろうか。
前述の国宝『伴大納言絵詞』とほぼ同時期に行われた敷曼荼羅の補彩は、やはりその頃用いられはじめた“地色補彩”を基本として色の選択を行おうとしたという。しかし、絵画の中に空間という面積の大きい色面があり、そこを地色の基本に据えることのできた前述2作品のような物語絵巻と異なり、敷曼荼羅の地色とは何なのかというところで、まずかなり悩んだということであった。その結果、敷曼荼羅の中で最も多用されている群青と緑青の部分がこの作品の地色にあたると定め、色を選んで補彩を進めていったという。しかし、それを渡邊氏に「違う」と否定された為、岡氏は渡邊氏に「どう違うのですか」と尋ね、それを皮切りに補彩を行う技術者側の窓口であった岡氏と文化庁の技官であった渡邊氏は、3日間にわたって敷曼荼羅の補彩の内容についての討議を重ねたという6。色や質感を言葉のみで言い表すのは非常に難しいことである。その時行われた討議は、作業を行う側と指導する側が共通する言葉や認識を一から探るようなものであったと推測する。
岡氏は「今から思えば、渡邊氏は色のみではなくマチエール7について言及されていたのだろう」と振り返る。当時、色を主体として作業が進められていたが、敷曼荼羅は絹の上に絵具を隙間なく載せて描かれた絵画である。そして欠失箇所には新しく補修絹が補填され、絹目が露出している。渡邊氏は、絵が欠失した箇所をどのような質感で見せるか、という点から話をされ、作業を行っていた側は色味を中心とした話をしていたため、初めは話が噛み合わず、かなり激しく議論が繰り返されたということであった。それは技術者側にとっても苦い思い出となったようである。しかし、ここで初めて、補彩という工程を行うことで作品の何を見せるのか、どこを見せるのかというところにまで及ぶ深い話し合いが行われ、そしてそれがあったからこそ、その後、指導する立場とそれを受ける立場との間でより共通した言葉や認識をもつことが出来たのだろうと考えられる。また、この双方が苦心した過程によって“地色補彩”についての考え方がより多様性を持ったものになったとも言えるのである。
それから5年後の1975年(昭和50年)に修理が行われ、詳細な記録と共に報告書が発行された国宝『仏涅槃図(応徳涅槃図)』(金剛峯寺所蔵)においては、絹本仏画における補彩の難しさが具体的に記録されている。沢山の鮮やかな色彩が用いられ描かれた本作品については、これまで絵巻で使ったような単色による地色補彩の方法ではどうしても部分的に齟齬が見られた。結果、線を描き入れない、繕い以外にはいかなる色も載せないという基本方針は守り、あくまで中間色(地色)による補彩をベースとしながらも、主に4種の補彩の方法を採らざるをえなかったと記述されている8。
以下に、報告書の補彩に関する記述を引用する。
*************************
B、本図における補彩
この補彩に関しては、まず委員会で討議された。その方針の大要は次の通りである。
a、全体としては、重くならず、できる限り基本色による地色合せにする。
b、線を描き入れることによる復元はしない。
c、釈尊の胸部の旧欠失箇所は、これを復元する。
d、上部の大きな旧欠失箇所から、沙羅双樹の幹の下部に至る中央に集中する損傷箇所については、細部を検討し決める。
これらの基本的方針に基づき、各部の状況を考慮に入れて、その都度検討を新たにして最善と思われる方法を捜し出し、本図の補彩を施した。
画面の多くをしめる余白、すなわち図柄の描かれてない部分に対する補彩は、以下のようにして行われた。
まず基調色を見つけ出してこれを作り、各部の色調の差異に応じて少しずつこれを変化させて補彩した。余白の部分にも、実際には何らかの薄い地塗り層が施されていた。この地塗り層の分析はされなかったが、肉眼観察によると全体にくすんだ黄土色に似た印象があった。これらのことから前述の基調色を黄土系の色調に決めた。
次に実際の補彩例をあげることにする。
① 上部中央、霞の部分
上部中央の大きな画絹欠失箇所、霞が描かれてある部分は、旧修理のいずれかにおいてオーバーペイント(穴部からはみ出して本画絹の部分にまで塗られてある)されてあった。このオーバーペイントの部分が、他の同様の部分よりもかなり暗い様相を呈していた。従って、この部分は周囲の色調に合わすと暗くなりすぎ、また、基調色では明るすぎるという結果が予想された。そこで実際には、基調色をやや暗くさせるにとどめて、より大きな視野からのバランスをとることに重点をおいた。
② 釈提桓因の顔及びその周辺部
画面中央に、帯状の長い欠損がある。これが沙羅双樹の花及び葉から下方へと伸びて、釈提桓因の顔部の中央を通過している。この欠失部を残存する顔の白色そのままに合わせて補彩した場合、その部分の印象が強くなる虞れがある。残存する顔の色の部分には、時代による濃淡や明暗がかなりあった。これらを中和する基調色を定め、この色調よりもやや明るいもので補彩し、顔部が柔らかく想像できるよう努めた。上部の白い花や緑色の葉にも同様の補彩を施した。
③ 釈尊の胸部
釈尊の胸部には、前述の如くきり込み式の補絹が施され復元補彩がなされていたが、顔料が変色し見苦しい外観を呈していた。
釈尊の肉身の絵具層の構造は、鉛白層とその上の黄色の薄い層であると考えられる。これはX線写真撮影の結果や、裏面からの観察で推定されたものである。今回の補彩では鉛白層のかわりに、貝殻胡粉を用いた。これは良質の鉛白が入手しにくいこと、現在の鉛白よりも安定性が高いこと、また後世の識別が容易であること等の理由からである。この白色層を用いて二通りのテストサンプルを作った。
白色層の上に通常の雌黄を被せ錆び付けしたものと、もう一つは同じ白色層の上に古い色墨(石田放光堂提供)の黄色を被せたものとである。
これらを東京国立文化財研究所保存科学部に依頼して経年テストを行った結果、後者がかなりの堅牢度を示したのでこれを使用した。方法としては、復元補彩を施した。
④ 沙羅双樹の幹
幹の下方で格狭間と接している部分に欠損があるが、ここでは白と薄茶との異なった二色の部分が接している。ここでは前述の補彩方法のうち②に近いものが採られた。幹の墨線の欠失部を想定して、これを境にして塗り分けた。
以上は、今回の補彩の四つの例であるが、修理の原則と委員会の方針をふまえて、実地に適する最善策としての補彩方法を見つけ出しそれを実施した。
(高野山文化財保存会編『国宝応徳仏涅槃図の研究と保存』上巻、東京美術、1983年、p.86~88より引用)
*************************
“4種の補彩”の内容を具体的に見ていくと、まず①は、いわば基本的な“地色補彩”(引用文中では基調色による補彩)に少し変化をつけたものであるが、②は全体から決めた地色とは別に、その部分のために別の“地色”を作ったということになる。そして③では、本紙とは識別可能な材料を用いて「方法としては復元補彩」を行い、④では基本的には行わないとしている、補填部分の色面内での塗り分けを行っている。つまり、場所によっては、“地色補彩”が使われる以前に行われていた方法を採っているという。これには、補彩の対象が宗教画であるということも大きな要因であると考えられる。③や④は、一見時代を逆行したかのように見える内容であるようにも思えるが、しかしここでのそれらは“地色補彩”が採用される以前のただ合わせていた補彩とは根本的に異なるものであり、本作品における補彩の中ではこれらも“地色補彩”の多様性を利用した方法の一つであると考える。これらを踏まえた上での報告書文中の「補彩の問題は、絶対的な回答に到達しえない」という言葉は、補彩という工程の難しさを端的に表しているといえる。
ここでもう一つ注目したいのは、岡氏がその方法を“採らざるをえなかった”と表現している部分についてである。その言葉を使うということは、「原則」としてある“地色補彩”の基本を一貫して通すことが不可能であったと述べているということであり、それはこの時点で“地色補彩”が「原則」としてしっかり存在しているということを文章で確認することが出来るからである。
第5節 小括
「(指定文化財の保存と修理を文化庁が指導・監督することとなる)以前の絵画の修理は、所有者や修理技術者の判断によって趣味的にあるいは恣意的に行われていた」9とされる。しかし、国が指定文化財の修理に責任を持つと定めたとき、「これまでのような個々別々の統一的基準なき修理が反省され」たとし、またその「反省も歴史的に見れば試行錯誤や統一的指導の不徹底の痕跡をいくらも見出すが、それにしても文化財という新しい概念を作り、修理に一定の手続きを定めるようになったところに、保存・修復の問題に対する新しい近代的な観念の成立があったといえる」10と、言葉ではこう表現されている。その中で、“地色補彩”、“基調色の補彩”、“地色に合わせた補彩”などと呼ばれる一見普通には思いつかないような手法が考え出され、使われ始めた1970年(昭和45年)頃は、大きな意味での変化が起こっていた時であったと考えられる。勿論すべての絵画の補彩に、この方針・方法が同じように適応されるわけではないが、絵画の修理全般への影響は決して小さく無かったと考える。つまり、そこではただ補彩の方法や技術が変わったというだけではなく、その“補彩”を行うことを選択するに至ったということで、技術者の絵画に対峙する意識自体が変わるという、日本の絵画修理において根本的な変化が起こった時期であるといえるのではないだろうか。
(第17回に続く)
《註》
1 “地色補彩”と同様に使用されている造語として“乾式肌上げ法”がある。これは、旧肌裏紙を除去する方法の一つで、肌裏紙全体を十分に湿らせた状態で一度に除去を行う“湿式肌上げ法”に対して、肌裏紙の除去する部分にわずかな湿りを入れ,少しずつ時間をかけて紙の繊維をほぐすように除去していく方法である。この乾式肌上げ法は,本紙の劣化が著しい場合や,裏彩色がある場合に非常に有効である。昭和50年代後半に現場で考え出され、名づけられた技法で、その名称は公式の書類や報告書でも使用されている。(“乾式肌上げ法”については、web修復第9回・第10回・第11回参照)
2 東京国立博物館『平成24年度 東京国立博物館文化財修理報告』ⅩⅣ、東京国立博物館、2014年、p.133
3 渡辺明義「文化財の修理について-特に日本画の場合」『在外日本美術の修復』中央公論社、1995年、p.142
4・5 渡邊明義「絵画の修理をめぐって-補彩の苦労を友とする」『守り伝える日本の美 よみがえる国宝』九州国立博物館、2011年、p.55
6 岡興造氏へのインタビューによる。その後2か月にわたって討論の内容を吟味し、その結果更に時間をかけて行われたのが現在の補彩である。渡邊氏はこれを見て「良いのではないか」と言われたという。
7 マチエールとは、材料・素材・材質をあらわす言葉である。ここで示すマチエールとは、端的にいうと本紙内で補彩が施された色面の質感を表していると考える。それは、基底材、彩色の材料や技法と大きく関係する。補彩箇所については、色とマチエール両方が非常に重要な要素であり、どちらかが条件を満たしていても、どちらかが不足していると、結果として違和感の拭いきれない結果になる場合が多い。
8 高野山文化財保存会編『国宝応徳仏涅槃図の研究と保存』上巻、東京美術、1983年、p.86~88
9・10 渡辺明義「文化財の修理について-特に日本画の場合」『在外日本美術の修復』中央公論社、1995年、p.134