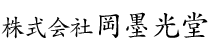2021年4月号:第10回 新しい材料と技術(3) 乾式肌上法の開発
岡 興造(談)
○湿式肌上法が適用できない修理作品
第9回では、乾式肌上法開発前の状況についてお話しました。第9回でもお話したように、もともとの肌上げ(=肌裏紙の除去)は湿式であり、技術者は湿式で安全にめくる技術を身に付けていました。技術者が水分による湿り具合や糊の硬さ、裏彩色の状態など総合的に見ながら行うため、工房や技術者の認識が大切です。特に裏彩色があれば、十分に時間をかけて進める必要があります。1時間ほど湿しておけば糊が緩むので、肌裏紙を少しずつ引っ張りながら、筆などで境界をおさえるようにして湿り気を与えつつ、じわじわとめくっていきます。鼠裏、墨裏と呼ばれるような暗い色の肌裏紙を湿すと真っ黒に見えますが、作業中、群青や緑青のように粒子感のある裏彩色が肌裏紙にくっついて取れそうになれば、熟練した技術者の目にはそれとわかります。しかし、黄土など具系の裏彩色の表面が肌裏紙と一緒にうっすらとれてしまったとしても、肌裏紙が濡れている間はわかりません。除去した肌裏紙が乾いてからぼおっと浮き上がるように白っぽく見えて初めて、少しとれていたことがわかるような状態でした。もうひとつ難しいのは、画面の面積が大きく裏彩色が多い場合で、数人の技術者で100cm角に1日が必要となります。そこで、第9回でお話したように、国宝《仏涅槃図(応徳涅槃図)》(金剛峯寺所蔵)の場合には、表打ちによる表面の養生と仮裏打ちを行いながら肌裏紙の除去をおこなう方法をとったわけです。白土の裏彩色が丈夫であったことも幸いしました。しかし、昭和57・58年度の重要文化財《孔雀経曼荼羅図》(松尾寺所蔵)の修理では、これまでの方法での肌裏紙打替がどうしてもできないという事態に直面しました。
《孔雀経曼荼羅図》の修理が始まり、修理前の調査を行ったところ、表面に厚く塗られた緑青や群青が酸化し、料絹から裏打紙までその影響が及んでいました。裏打紙は絵具焼けの影響でぼそぼそになっており、焦茶色に変色、炭化して、紙の繊維が破壊され、泥状の塊のようになっていました。和紙の柔軟性は失われ、総裏紙からして通常の除去方法は困難であり、肌裏紙に至っては紙の形状で除去することができない状態でした。著しく劣化した肌裏紙は、繊維が破壊され泥状になっているため、ピンセットでつまむ作業も困難であり、湿式で長時間水に浸す方法をとることができませんでした。
○複雑な絵画構造
この《孔雀経曼荼羅図》と同時期に国宝《十六羅漢像》(東京国立博物館蔵)の修理に携わることになりました(昭和57〜59年度)。《十六羅漢像》は絹目が比較的粗く、修理前の顕微鏡による観察で、絹目の間から表面とは異なる彩色が裏面に多く見られることがわかりました。第9回でお話した《応徳涅槃図》や重要文化財《両界曼荼羅図(敷曼荼羅)》(教王護国寺所蔵)のように、裏面から全面に塗られた白土のような白色顔料による裏彩色の例は、以前から多く経験してきていました。このような仏画の大幅の場合に、裏面全体に白土のような白色絵具等が施されていたのに対して、《十六羅漢像》は、裏面全体に彩色層があるということではなく、各尊像や建物、樹木などが表現された部分の裏面に、表面の色に対して別の色の裏彩色が施されていたのです。裏彩色は単色ではなく、幾色も駆使して個々の尊像ごとに丹念に施されていました。建物の金具の表現を例にとれば、裏面から金箔が貼られ表面からは墨線で文様が描かれるなど、表からの見え方を計算した裏面の表現と表側のテクニックがあいまって、色彩豊かで重厚な画面を構成しています。
《十六羅漢像》は16幅あります。1幅ずつの画面はさほど大きくないとしても、16幅を同じ状態で肌裏紙除去をし、同じ色で同じように肌裏打ちをおこなわなければ、一具のものとしてのそれぞれの仕上がりの印象が変わってしまいます。複雑な裏彩色があるために、時間をかけて肌裏紙除去をおこなう必要があることと、16幅同じ状態で作業を進めること、これを湿式肌上法で両立することは困難でした。
また、修理前に観察した結果から、《十六羅漢像》が多彩で複雑な絵画構造をもっていることは明らかであり、それを裏面からじっくりと調査したいという思いがあったことも否定できません。第9回でも少し触れたように、たとえば、湿式法で肌裏紙除去をした国宝《伝源頼朝像》(神護寺所蔵)の場合、顔部や笏、足の部分や足元の衣など、白色で表現された厚い裏彩色層については、湿っていても確認することができました。しかし、黒色の袍の部分は、湿った状態では、画絹の糸目の間に何があるかははっきりと確認することができませんでした。袍の文様などは目が詰まった表現がされていたので、今から振り返れば、必ず裏彩色があったのではないかと思います。もしあのとき乾式法であれば、何か確認できたのではないかと思えて残念でした。あわせて、林功氏1が模写をしたときに、この袍の黒色の表現と文様部分の表現がわからず、困っていたことも思い出されます。絵画技法に対しても、乾式法による裏面からの観察をすることで、技法の解明が進んだのではないかと思います。修理時にはいろいろなことを知ることができることを忘れてはならないと考えます。このような経緯もあったため、《十六羅漢像》については、16幅を表打ちしておいて乾燥した状態で調査することができれば、面白いことがいろいろわかるだろうという期待がありました。
○表打ちのヒント
ふりかえってみれば、大きな変化があるときには同時に複数の課題が重なっているように思います。乾式肌上法の場合には、《孔雀経曼荼羅図》と《十六羅漢像》の2件の修理を同時に抱えていたことで、新しい技術が達成されたように思います。これら2件の修理前に、既に《応徳涅槃図》の修理経験から、大幅の肌上げについて、部分的に仮裏打ちと表打ちを繰り返しながら作業を進めることができるという感触を得ていました。これは乾式肌上法に限ったことではありませんが、どの修理が直接的に技術開発に結びついたということではなく、さまざまな経験と修理工程上の必要性があわさって、生まれたものだと思います。
実は、表打ちについては、私が中学校へあがるかどうかという時に、その技術を見ていました。昭和30年頃のことですが、墨光堂では大谷探検隊が明治期に持ち帰った壁画の修理をしていました。現在は東京国立博物館に所蔵されているベゼクリク石窟の壁画等です。修理前は、厚みが10cmほどあった壁体のバランスが悪く、表面の薄い絵画層まで亀裂が入っていました。絵画層を安全に保存するために壁体の厚みを5mm程度にまで薄くする方針がとられました。このとき、アクリル樹脂で固められた壁体を削るために、作業前に紙や布によって表打ちをし、絵画表現を保護してから裏面を削り取るという作業をしていました。これが私の記憶にある、表打ちを初めて見た経験です。
昭和56(1981)年に中国で見た表打ちの方法も印象に残っています。当時はまだ中国に個人旅行に行くことができず、国宝修理装潢師連盟の連盟員と京都の表具師と15人で日中友好協会の団体として中国を訪れました。北京、上海、西安の博物館の修理所を見学しましたが、表打ちの作業は北京で見ました。油紙のような紙で表打ちをして肌上げをしており、このときは、面白い方法があると思って見ておりました。他にも、油彩画の修理をするときに、裏面からの作業や補強のための和紙で表打ちをする工程を見たことがあります。
かつてベゼクリク石窟壁画の修理を見た経験が印象深かったこともあり、私は壁画修理に大きな興味を持ち続けておりました。平成の初めにはよく中国に行き、壁画の修理を西安で見せてもらっていました2。あるとき、特別に発掘現場の見学が許可されました。発掘中の墳墓内やそこに描かれている絵を見ることができ、さらに壁画の剥ぎ取りという私にとって大変興味深い作業を見ることができました。現場では、桃樹脂(自然アラビアゴム)を濃いめに煮た液でガーゼを貼り付けて表打ちをし、壁画から約1cmの厚さで剥ぎ取られ、そのままの状態で博物館の収蔵庫に入れられていました。
今お話したのは、時間も場所もさまざまな場所で見てきた経験ですが、いずれも本体を修理するための補強であり、本紙表面を保護するためにされたものでした。このように見てきたことがすべてではありませんが、これらの経験が《応徳涅槃図》の修理の際に表打ちで保護をして肌裏紙除去をするという発想の手助けになったのではないかと思います。そして、その《応徳涅槃図》の修理経験が《孔雀経曼荼羅図》と《十六羅漢像》での乾式肌上法の採用につながったわけです。思い出してみれば、いろいろな経験が要因となって、表打ちに至ったということがわかります。
表打ちに用いる接着剤の選定は、《伝源頼朝像》の修理経験がヒントになりました。修理前の《伝源頼朝像》には、絵具の剥落止めのためと思われる厚めの接着剤が表面から塗布されていました。水を用いてこれを除去し分析したところ、布海苔と思われるものであったことが判明しました。表面を補強するための表打紙を貼るということは、表打紙を取り外した後にも微量の接着剤が表面に残留することを想定しておかなければなりません。選定する接着剤によっては、時間の経過で変質したり、絵画面の表層を引っ張ったりして、絵具の剥離の原因になる危険性も考えられ、最も注意が必要なところです。《伝源頼朝像》の経験から、表面に塗布した布海苔は、絵画表面に影響を与えず取り除くことができることがわかりました。私たちがよく使用している伝統的な材料であり、性質をよく知っている布海苔を使って、表打ちを安全に行うことができるという目処が立ちました。このようなことから、今まで経験してきたことを踏まえて、表打ちをおこなって補強した本紙に対して、裏面から少量の水を与えて肌裏紙を取り除く方法、すなわち乾式肌上法の採用に踏み切ることができました。
○乾式肌上法の採用
《孔雀経曼荼羅図》については、表打ちをし、時間をかけて物理的に肌裏紙を解体していきました。これまでの方法としては、刃物などで削り取るなど物理的な処理を検討するしかありませんでしたが、少しずつ湿りを入れて紙繊維を取っていく方法で、肌裏紙除去を進めることができました。
《十六羅漢像》については、技術者を数幅に分け、平行して肌裏紙除去を進めました。作業は、肌裏紙を薄くするように、3分の1ずつ紙の層を除去します。裏彩色に近づくにつれ技術者には熟練が求められますので、最初の3分の1は経験年数の浅い人でも担当することができ、最後の3分の1は経験豊富な技術者に任せました。このような進め方をすれば、技術者の習熟度に応じてチームとして合理的に作業を進めることができます。時間をかけて紙繊維の除去を進め、乾燥後、裏彩色の上に旧肌裏紙を接着していた糊の層が見えたとき、安全に裏からの表現を守ることができたとわかりました。当初心配していた16幅全体の修理後の見え方についても、違和感のない仕上がりにすることができました。
湿式の場合は肌上げ後すぐ新しい肌裏紙を打っていましたので、乾いた状態で裏面を見るのは初めての経験でした。絵具の状態がよくわかり、各幅を比較しながら時間をかけて裏面の調査をし、記録をとることができました。1幅ずつ細かい図面や資料を作成し多数の写真を撮りました。その一部を『修復』誌上でご報告しています。
乾式肌上法は、小面積の作業であるため、1幅の作品に対して多くの技術者が同時にかかわることができます。そして、湿式のように時間との戦いではなく、安全に時間をかけて作業を進めることができます。昭和50年代後半のこの2件の修理を通して確立した新しい作業工程は、作品を安全に守り、絵画表現についての詳細な調査と記録を可能にするなど、多くの結果が得られるものでした。乾式によって可能となった修理の方法については、次に詳しくお話したいと思います。
(第11回に続く)
1 林功氏は日本画家で当時は東京芸術大学に所属しており、文化庁の依頼で復元された絹目の画絹に現状模写を行なっていた。この時の調査で損傷の進行が確認され、数年後に伝源頼朝像ほか3幅対の修理が始まった。模写において、同技法・同素材をおこなった第一人者。
2 西安市の北にある恵荘太子(玄宗の兄)の唐代墳墓。