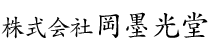2021年2月号:第9回 新しい材料と技術(2) 乾式肌上法の開発前夜
岡 興造(談)
○昭和50年代の変化
電子線劣化絹など開発してきた昭和40年代が終わり昭和50年代に入ると、文化財修理の予算が増え国指定文化財の修理件数が多くなってきました。仏画や絵巻、肖像画、水墨画、書跡、古文書など様々な文化財の修理に取り組むことで、修理に必要な考え方、それに対する技術を改良するなどして、工房の技術力が向上したように思われます。修理に必要な考え方という点では、考古品の修理の専門家や、絵具や絵画技法を知悉する模写の専門家、保存科学の専門家など、装潢以外の世界の人々との交流によって知りえたこと、考えるようになったことが大きいと感じています。他の領域の専門家との意見交換や技術交流は、保存を目的としたものの見方、考え方の訓練になりました。また、昭和50年代には、修理環境を変える大きな出来事がありました。昭和55年(1980)7月、京都国立博物館の中に念願の文化財保存修理所ができたのです。修理予算が増え、修理環境が整ったことで、若い人の育成をしやすくなりました。
電子線劣化絹の開発は父と進めてきましたが、昭和50年代は、私自身、父の助手という立場から徐々にキャリアを積み重ね、新しい課題に取り組むようになりました。このとき修理技術に関する大きな課題のひとつとして、絹本絵画の裏打紙を取り替えるときの肌裏紙の除去方法がありました。後に「乾式肌上法」と呼ぶようになる肌裏紙除去方法の開発は、昭和50年代後半に本格化します。今回は「乾式肌上法」の開発に至った経緯のお話をしたいと思います。
○応徳涅槃図の修理
乾式肌上法の開発までの道筋を振り返ると、昭和50年(1975)、国宝《仏涅槃図(応徳涅槃図)》(金剛峯寺所蔵)の修理が大きな意味をもっていました。本件については第3回でも少しお話したのですが、この仕事から始まったことが多くあり、本題に入る前にもう少しお話しておこうと思います。
応徳涅槃図の修理は、私たちの工房にとって非常に大きな仕事でした。このときはまだ文化財修理所の開設前ですので、通常であれば自宅工房にお預かりして作業することになります。門外不出の文化財ですので、高野山に出張して作業を行うか、または高野山から下ろしてお預かりするのか、大決断が必要でした。このときは、町中でお預かりするのは危険があるのではと懸念され、当時の京都国立博物館の館長であった松下隆章先生からのご提案によって、博物館内の技術参考資料館の模写室で修理作業を行うこととなりました。修理委員会が設けられたのも、私たちが経験するなかでは初めてのことでした。
委員会は修理期間中に計4回開催されました。松下隆章先生、源豊宗先生、梅津次郎先生、高野山霊宝館の山本智教先生、日本画家の上村松篁先生、そして文化庁の濱田隆先生と渡邊明義先生、和歌山県文化財保護課の担当者が委員になられました。私たちは修理の進行と工程ごとの本紙の状況を委員会に報告し、協議によって修理方針が決定されていきました。
このときの修理方針として、補彩や補筆が加えられた旧補修絹はすべて取り除くことになりました。取り除く旧補修絹の位置を正確に記録するため、線描きで写した原寸大の図面を作成し、旧補修絹が嵌められていた位置に貼ることにしました。旧補修絹のうち釈迦の胸の部分は大きなもので、除去すれば大きく印象を変える部分でした。しかし、経年により旧補修絹上の色が変化して目立っていたため、この部分も原則に従って除去しました。そして、新しく補填する補修絹には、他の補絹箇所とは異なり、復元補彩をすることが委員会で決定されました。絵絹を復元し、白土下地、朱を中心に色墨を使用して色合わせをし、多くのサンプルを作製しました。それらの中では色墨で作られた色が一番となり、色墨については放光堂さんの協力を得て古墨の色墨を使用しました。これらのサンプルは東京国立文化財研究所(現・独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所)に依頼して劣化テストを行い、そのなかで最も安定していたものを選択し、委員会で作製方法、補填方法の了解を得て、補填しました。
また、第3回でも触れたように、記録を正確にとること、写真を多く撮影することを意識して進めました。修理中にしか見ることのできない裏面の情報をカラー写真で克明に撮り、全面をエックス線で撮影、数多くの写真記録をとりました。これらの記録は、後に出版された本(高野山文化財保存会編『国宝応徳仏涅槃図の研究と保存』東京美術、1983年)に掲載され、活用されています。このように、この時代にできるだけのことを考えてやっていました。
○大画面絵画の肌裏紙取り替え
では、肌裏紙取り替えの話へ進みましょう。絹本絵画の修理において、肌裏紙の取り替えは最も困難かつ修理の根幹となる作業です。当時の一般的な肌裏紙除去方法は、現在「湿式肌上法」と呼ばれている方法です。まず、作業台に水を打ち、本紙表面を伏せて皺が発生しないよう平滑に作業台に貼り付けます。そして、本紙の裏面から噴霧器や水刷毛によって水分を浸透させ、本紙と肌裏紙を接着している糊を緩めて肌裏紙を除去します。その後、本紙が乾燥しないうちに新しい肌裏紙を接着させます。一連の工程中、本紙が乾燥することを防ぐため多くの湿りを与えることになります。水分を与えるということは、絵画表現を支えている膠そのものを軟化することにもつながりかねませんし、水分によって汚れが移動する危険性もあります。このため、作業は短時間に手早く完了する必要があります。
応徳涅槃図は縦267.2cm横269.0cmという大画面であったため、一般的な方法で素早く肌裏紙を除去するということができません。そこで、レーヨン紙による表打ちを施し絵画表現を保護した上で、裏からピンセットで肌裏紙を持ち上げるように除去し、除去が完了した部分にレーヨン紙による仮裏打ちを行うことを小面積ごとに繰り返しました1。この方法をとるためには、表面の絵具の点検をしっかり行う必要があります。仮裏打ちに耐えることができるよう、必要十分な剥落止めを行いました。そうして元の肌裏紙を除去したところ、元の肌裏紙には色のついた糊で料絹に接着されていることが判明しました。黒っぽい具が混ぜられた色糊は、元の肌裏紙を除去した後も画絹の絹目の間に残り、これを徹底的に取り除こうとすれば絵具に危険が及ぶことから、画面への負担なく除去できる箇所のみ取り除くという方針が取られました。
新たに肌裏紙を打つにあたっては、4通りに染めたサンプルを用意しました。現在の修理ではしばしば行われる検討過程ですが、これも部分的な仮裏打ちができたからこそ実現した初めての試みでした。料絹のすぐ裏を支える肌裏紙の色調は、修理後の見え方に大きく影響します。修理前の肌裏紙は墨色というほど暗いものでした。暗い肌裏紙は画面の汚れや傷を見えにくくしますが、同じように繊細な絵画表現も隠してしまいます。修理にあたってはより明るい色が検討され、修理委員会で見え方が比較検討されました。薄い茶色の肌裏紙で仮裏打ちを行ったところ、修理前には見難かった純陀眷属の持物の文様がはっきり見える、羅漢の肌の色が違って見えるなど、明らかに見え方が変わることがわかりました。描かれた当初の見え方に近づけるならば、明るい色の肌裏紙が適切です。しかし、ここで問題になったのが、過去の修理で用いられた色糊の跡でした。明るい色の肌裏紙を用いると、絹目に入り込み除去できない色糊の痕跡が表から黒く点々と見えてしまいます。委員会で検討された結果、自然の楮紙の色と旧肌裏紙の中間の色合をもつ古色がかった茶色が選定されました。結果として、修理前のイメージを大きく変えることなく、修理前よりも明瞭にディテール表現を見ることができる仕上がりとなったと思います。このような検討を通して、肌裏紙のもつ影響力の強さ、重要性が改めて認識されました。
○乾式肌上法開発への布石
短時間に肌裏紙の除去をすることが不可能であるという応徳涅槃図の修理を通して、表打ちによる表面の養生と仮裏打ちを行いながら肌裏紙の除去を進めることができるとわかりました。この涅槃図の裏彩色は個々の尊像の描写に合わせて塗り分けられず、裏面より画面全体に白土のような白色顔料絵具が塗られ目詰めされていました。この白土のような裏絵具層が大変丈夫であったこと、裏絵具によって微妙な絵画表現がなされてはいなかったことが、肌裏紙除去作業を進める上で幸いしたと言えます。それまでにも、国宝《両界曼荼羅図(伝真言院曼荼羅)》や重要文化財《両界曼荼羅図(敷曼荼羅)》(いずれも教王護国寺所蔵)の修理の際に、同じような裏絵具があるように見えたことがありました。ただ、水分を含んだ状態で観察したために、はっきり細かい状態まで観察することができませんでした。この時代の肌上げの限界であったと今は思っています。
このあと、現在と同じような乾式肌上法が修理に適用されるのは昭和57・58年度の重要文化財《孔雀経曼荼羅図》(松尾寺所蔵)であり2、研究報告として発表することができたのは、昭和63年(1988)に京都で行われたIIC(国際文化財保存科学学会)国際会議3のときでした。「乾式肌上法」という用語は、このIICの発表の際に、東京国立文化財研究所の増田勝彦先生に相談して名付けたものです。
応徳涅槃図の修理を終えた父は、修理報告のあとがきに次のように記しています。
絹本の肌裏をめくっている途中で、画面では見られない線や下層の絵具が濡れた絹を透かしてはっきりと現れてくる。慌ててカメラやライトを用意して撮影するのだが、肌上げの最中といえば、片時も目も手も離せない時であるし、第一に緊張と集中とで写真を撮ることなど忘れてしまったりする。また、湿り加減が大切なこの場面では、撮影のための照明の熱は大の嫌われ者でもある。大仰に言えば、周到な修理と克明な記録とは、もともと相容れないところがあるのかもしれない4
時間をかけて安全に肌裏紙除去作業を行うことを可能にした乾式肌上法の開発は、結果として裏面からの詳細な観察と記録を可能にしました。「周到な修理と克明な記録」は今日ますます精緻に行われるようになってきています。振り返ってみれば、父がこのような言葉を残した応徳涅槃図の修理は、乾式肌上法開発のための大きな布石であったように思います。
(第10回に続く)
1 作業の詳細は「応徳仏涅槃図の修理」『国宝応徳仏涅槃図の研究と保存』(東京美術、1983年)をご参照ください。
2 このことについては、次回お話します。
3 第1回IIC世界大会に参加した父は、東洋で初めて開催されるこの京都での国際会議に出席したがっていましたが、病気をしており昭和60年頃から入退院を繰り返していたため、残念ながら参加がかないませんでした。会議では、第1回IIC国際大会にも日本から参加していたことを発表するため、父が東京芸術大学教授の寺田春弌先生らと参加したときの写真(第8回掲載)が会場の大画面に写し出されたことを思い出します。
4 前掲注1