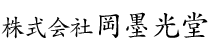2021年1月号:第8回 新しい材料と技術(1) 電子線劣化絹の開発
岡 興造(談)
現在、当たり前のように使われている修理材料のなかには、半世紀前に試行錯誤を経て生まれたものがあります。その代表的な存在が電子線劣化絹です。今回はその開発のお話をしますが、まずは電子線劣化絹が生まれる前の状況から始めたいと思います。
○西洋の修理と東洋の修理
表装の仕事は、紙を切る、糊を付ける、裏を打つ、糊には新糊と古糊があって使い分ける、打刷毛を打って軸物の形にする、裂地の取り合わせを考えるという流れで行われ、基本的なところは百年来あまり変わらないと思います。修理材料、修理技術に関する大きな変化があったのは昭和40年代のことでした。
 昭和25年に文化財保護法ができ、昭和30年代になると補助金による保存修理事業が円滑に進むようになります。現在の文化庁による修理技術者講習会も、その頃始まりました。そのような流れのなかで、技術者たちに専門意識が芽生え始めます。欧米から保存修復の専門家が来日し、交流がさかんになったのもこの頃でした。話を聞くと、欧米では修理理念が根付いていて、油絵の修理、紙の修理、フレスコ画のような壁画修理など、大学でも教えていることがわかりました。父から聞いたことですが、教育という点で、日本は数十年くらい遅れているように感じたそうです。父が欧米との差を実感した大きな出来事は、1961年にIIC世界大会に参加したことでした。IIC(国際文化財保存科学学会)は1950年に設立され、修復保存技術者やこの分野の科学者、歴史家といった学者たちも一緒になって考える国際機関です。父が参加した1961年の大会は設立10周年を記念した大会でした。その時点で欧米にはすでに修理の専門性に関して10年の蓄積があるということです。議論の基盤がそれだけ違うということですが、それ以前に西洋の修理と東洋の修理には大きな違いがあることもわかりました。根本的な違いは、油絵の修理というのは絵の修理だけで、額は別に考えられているということでした。建築にしても、建物は建物、壁画は壁画と分けられていました。西洋で絵画の保存というと中心は油絵の保存ですが、そこでは絵具の成分分析や絵画性がディスカッションされます。では、日本で絵の修理を誰がしたかというと、画家でもなく表具屋さんです。一般的な表具屋さんにとって修理は仕立ての一環です。東洋の書画は、西洋のようにそれぞれが独立した専門分野ということではなく、複合的な技術の中で取り扱われてきたということもできます。東洋と西洋の違いみたいなもの、私たちがそれに目覚めたのが1960年頃でした。
昭和25年に文化財保護法ができ、昭和30年代になると補助金による保存修理事業が円滑に進むようになります。現在の文化庁による修理技術者講習会も、その頃始まりました。そのような流れのなかで、技術者たちに専門意識が芽生え始めます。欧米から保存修復の専門家が来日し、交流がさかんになったのもこの頃でした。話を聞くと、欧米では修理理念が根付いていて、油絵の修理、紙の修理、フレスコ画のような壁画修理など、大学でも教えていることがわかりました。父から聞いたことですが、教育という点で、日本は数十年くらい遅れているように感じたそうです。父が欧米との差を実感した大きな出来事は、1961年にIIC世界大会に参加したことでした。IIC(国際文化財保存科学学会)は1950年に設立され、修復保存技術者やこの分野の科学者、歴史家といった学者たちも一緒になって考える国際機関です。父が参加した1961年の大会は設立10周年を記念した大会でした。その時点で欧米にはすでに修理の専門性に関して10年の蓄積があるということです。議論の基盤がそれだけ違うということですが、それ以前に西洋の修理と東洋の修理には大きな違いがあることもわかりました。根本的な違いは、油絵の修理というのは絵の修理だけで、額は別に考えられているということでした。建築にしても、建物は建物、壁画は壁画と分けられていました。西洋で絵画の保存というと中心は油絵の保存ですが、そこでは絵具の成分分析や絵画性がディスカッションされます。では、日本で絵の修理を誰がしたかというと、画家でもなく表具屋さんです。一般的な表具屋さんにとって修理は仕立ての一環です。東洋の書画は、西洋のようにそれぞれが独立した専門分野ということではなく、複合的な技術の中で取り扱われてきたということもできます。東洋と西洋の違いみたいなもの、私たちがそれに目覚めたのが1960年頃でした。
○絹を弱める方法
ちょうどその頃、ひとつの課題がありました。絹に描かれた絵画を修理しようとすれば、穴が空いているところには絵絹を埋めて、画面を安定させなければなりません。これは昔からずっとおこなってきたことですが、埋める絹をどうやって調達するかが問題です。昭和30年代までは、骨董市などで買ってきた古画の無地部分を使うようなこともしていました。しかし、次第にこのような古画の断片を得ることは難しくなり、一方で昭和30年代から始まった国の補助金による保存修理事業が増え始め、補修絹が不足し始めたのです。他にも、掘りごたつの中に絹を入れて置いたり、蔵に数年間吊っておいたり、古びさすことをしていたようです。また修理のときに除去した伏裏絹(欠失箇所をふさぐように大きめにあてられた補修絹)の再利用をはかるなど、さまざまな方法で古画の修理に適した補修絹を確保しようとしましたが、うまくいきませんでした。この頃は、古いものは弱くなっているから、古画に埋めたときに力のバランスが釣り合うという発想ではありませんでした。オリジナルと補修部分の強さを合わせたいという考えではなく、新しい絹特有の艶や硬さをなくし、古画の雰囲気に添うように糸が痩せて弱くなった絹を求めていました。
昭和36年頃すでに父は、交流のあったボストン美術館の技術者から、エックス線のようなもので絹が弱くなるということを聞いていたそうです。昭和40年には東京国立文化財研究所(現・独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所)の樋口清治氏に相談に行っています。前回までお話してきたように、ちょうどその頃に入社した私は、裂の復元と平行して新しい補修絹を考えることになりました。昭和40年代には、保存科学に関する文献を日本語で読む環境も整ってきました。若い技術者が工房に入ると、プレンダリース博士の翻訳本(H. J. プレンダリース『古代遺物及び美術品の保存』国宝修理装潢師連盟、1967年、Harold James Plenderleith "The Conservation of Antiquities and Works of Art -Treatment, Repair, and Restoration-", Oxford University Press, 1956)や、登石先生の本(登石健三 編著『古美術品保存の知識』第一法規出版、1970年)を読むように勧められ、科学的な視点をもつことを教えられるようになりました。
新しい補修絹の話に戻りますと、古画に合う絹を安定的に確保するという難題を抱えた私は、裂の復元でも紹介した廣瀬さんに相談し、同志社大学の北側にあった京都市染織試験場(現・地方独立行政法人京都市産業技術研究所)にも行きました。京都市染織試験場では、ここでの試験は物の耐性を確認する目的のものばかりで、絹自身を弱くする方法は聞かれたことがないと言われたことを覚えています。色の褪色実験をする機械で紫外線にあて湿度を上げることで弱くすることはできましたが、いかんせん小さな面積での実験しかできませんでした。また、ドイツ製の大きいガスオーブンで高温多湿の状態を作りその中に絹を置くことも試しましたが、熱で練れてしまうなどうまくいきませんでした。そのようななか、昭和40年代のはじめに、家庭用ターンテーブル式電子レンジが発売されました。これがガスオーブンと同じような調理器具で熱の出ないものでした。大変高価であったため、メーカーの研究所に勤めていた友達に頼んで電子レンジを借り、絹を入れて中央に水を入れたコップを入れて長時間回してみました。すると、取り出した絹は、茶色味を帯びていたものの、手で少しだけ破れる程度に弱っていたのです。しかし、この実験を長時間行ったため、借りた電子レンジのターンテーブルは熱で歪み破損してしまいました。高価な器具を壊してしまったことで大変びっくりしましたが、貸してくれた友人からは、かえってこの商品の弱い部分がわかってよかったと言われ、ほっと胸をなでおろしました。
この電子レンジで弱くなった絹を持って、かねて相談をしていた東京国立文化財研究所の樋口氏の元を訪ねると、日本原子力研究所 高崎研究所(現・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 高崎量子応用研究所)を紹介されました。こうして電子線の照射による劣化実験が始まりました。詳しいことは樋口先生の論考に書かれているのでご参照ください(樋口清治「軸装作品の保存と修復−−電子線による補修用絹の劣化促進処理」『表具の科学』東京国立文化財研究所、1977年)。
ベルトコンベヤの上に絹を置き電子線を照射すると、接する面が熱を持ち、熱くなり過ぎて焦げてしまいます。バトンの上に絹を張るように設置して照射しても、バトンと絹の間に熱がこもります。何度も目の前で持ち込んだ絹が燃え上がり、失敗を繰り返しました。こうしていろいろな工夫をするうち、バトンの下から空気を抜き、熱を逃がすようにしたところ、中央部分は絹が焦げ色になったものの周囲は使用可能な状態でした。はじめは折りたたんで照射していましたが、熱を逃がすためにバトンの大きさに合わせた30cm×90cmで絹を切り重ねて照射するようになり、現在の方法に辿り着くまでに2年を要しました。こうして実験開始から2年後にやっと人工的に強度を弱めた補修絹「電子線劣化絹」を作ることができました。
○絹本修理のスタンダードに
ようやくできた電子線劣化絹を最初に文化財修理に使ったのは、群馬県指定文化財《十六羅漢図》(長楽寺所蔵)でした。また、昭和45〜47年度にかけて修理を行なった重要文化財《両界曼荼羅(敷曼荼羅)》(教王護国寺所蔵)は料絹欠失部分の総面積が大きく、電子線劣化絹なしには修理が困難であった事例です。修理の対象となる書画の材質や経年度合はそれぞれに違っており、それに対応することができるよう、劣化させる絹そのものの織り方の工夫もおこなわれるようになりました。電子線劣化絹の開発は現在も続いており、現在では130種類以上の絹から、修理対象の料絹に合ったものを選択できるようになっています。
電子線劣化絹は、現在では絹本文化財の修理に欠かすことのできない材料ですが、開発後すぐに普及したわけではありません。昭和40年代には他の工房はどこも使用してくれず、劣化の費用や高崎へ通う交通費が高額であることからも、他工房の協力を得るのが難しかったことが思い出されます。文化財修理への使用が一般的になったのは、東京国立文化財研究所から昭和52年に『表具の科学』が出版され、先にご紹介した樋口先生のご論考が発表された後のことです。日本原子力研究所 高崎研究所や東京国立文化財研究所、文化庁の協力によって、現在のように国宝修理装潢師連盟に加盟する各工房で使用されるようになりました。電子線劣化絹の例は、技術者の意識に育ち始めた科学的なものの見方が新しい材料を開発し、時間をかけて当たり前の修理材料となった過程を示す好例ではないかと思います。新しい材料はそれに合った新しい技術を生み、新しい考え方を生みます。電子線劣化絹の開発によって補修絹補填の技術も改良を重ね、現在のようになりました。これも何年もかかって進化した技術の例といえます。
(第9回に続く)