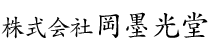2023年7月号:第18回 日本の文化財修理における“地色補彩”について(5)
亀井 亮子
○第3章 イタリアにおける文化財修復と補彩の歴史
第3節 中間色による補彩
中間色とはイタリア語でNeutroと言い、田口かおり氏によると、その意味は“何色とも定められない色”とされている1。この技法はチェーザレ・ブランディが新しく考え出したというわけではなく、元々は19世紀の初頭から主に建造物や壁画の修復において使用されていた技法であり、それをブランディが後に絵画の補彩に採り入れたということのようである2。
ブランディは他の工程同様、補彩についても理論的に成立するよう心を砕いた。既存の介入方法への否定から、あえて中間色による補彩を提唱したのである。その方法を使った“成果”として最もわかりやすい作品は、シラクーサのパラッツォ・ベッローモ州立美術館蔵アントネッロ・ダ・メッシーナの『受胎告知』であろう。この作品は1940年(昭和15年)に、過去(1914年・大正3年)に施された補彩を全て除去し、それまでの行為(過ぎた介入)に対する批判を込めて、新たに理論と倫理を尊重した補彩が施された3。そして一定の期間、「知覚するに際し、空白が最前面に浮かび出るのを和らげるために、できるだけ特徴のない色調で空白を奥へと押し戻す」4という理想の下、ブランディが指揮するローマ国立中央修復研究所において、様々な作品で中間色による補彩という試みが続けられた。その動きはローマのみならず、フィレンツェにも見られる。1966年(昭和41年)のアルノ川大洪水の際に被害を受けた絵画の修復に、フィレンツェ国立修復機関のウンベルト・バルディーニがブランディの中間色補彩の技法を改良して使用した例が確認できるのである5。
しかし中間色で補彩された作品は、「実際に鑑賞者が中間色による補彩を目の前にしたとき、あたかもばらばらの破片から再構築されたようなイメージは、その潜在的な統一性を失っているかのようにみえ、鑑賞者を戸惑わせることになってしまう」6と田口氏も指摘するように、鑑賞者に違和感を生じさせるものであった(一般の鑑賞者には理論や哲学による定義付けは意味を成さない)。そして“中間色”による補彩は、鑑賞者のみならず研究者からも不評を買い、アレッサンドロ・コンティを筆頭に、多くの人々に批判され否定された。ついには後年ブランディ自身も「良い方法ではなかった」と述べるに至っている7。田口氏は「1970年代後半までに「中間色」は修復現場からほぼ完全に姿を消してしまった」とし、それは「短命だった過去の奇抜な技法」であったとしている8。
美術品の蒐集家であり美術史の研究者でもあるロベルト・ロンギは、作品の欠失箇所に対する対処について「よくよく考えてみるに、観者の目を極力妨げないようにするには、欠落が欠落としてはっきり意識できるようにしておくしか方法はない。ただそうすることによってのみ、肉眼―ここでは網膜のみならず、直覚的な判断力を指している―は、たやすく欠落部分を抽象し、ただ「精神的」に、心のなかでだけ、それを復元することができるであろう」と述べている。しかし、ブランディはロンギのように人間の想像力に完全な信頼を置くことを好まず「芸術作品の経年の痕跡を消すことなく」「歴史的な埋造を冒すことのない」介入を推奨し、彼の中間色を「想像力によって欠損部分の空白を補完することを避けるために採用した技法である」と述べている9。
ブランディの色彩補完における絶対的なルールは「介入箇所がオリジナルから明確に差異化され、なおかつ不用意に目立たないこと」とし、「剥き出しの欠損部分による物質性の主張を抑制し、なおかつ作品のイメージから一歩下がった背後の位置で謙虚に留まるという新たな補彩の可能性」10を探ろうとしたが、しかし結果、彼自身のなかでも「どれほどにニュートラルであると思われる色彩も、オリジナルのイメージを構成する色彩の力を弱めてしまう」11という結論に達したのである。
第4節 その他の地域における絵画修復と補彩について
もう一例、日本とも関係が深いと思われるベルギーの様子も見ておくこととする。
ベルギーでは、補彩はillusionnismeと呼ばれており、その方法は「欠損部を単に目立たなくするカモフラージュでもなければ、亀裂まで入れて補彩部分がどこにあるかわからなくする偽造でもない」と森直義氏は述べ、また「非常に近い距離では補彩として認識できるが、失われた連続性を回復して適正な距離で作品全体の「読み取り」を可能にするもの」としている。その補彩についての考え方や基本的な立場は、おそらくポール・フィリポが洗浄に関する論文を発表した1960年代から現在まで変わっていないということである12。
ベルギーにおいて修復の第一人者とされるポール・コルマンスは科学と修復を融合したベルギー王立文化財研究所最初の保存科学者であった。彼にはアルベール・フィリポという腕のたつ修復家の同僚がおり、2人は共同で様々な修復を行っている。
ベルギーの修復における独自性は、戦後まもなくという早い時期に今日の修復の基本要件をみたす修復が行われたというところにあると蜷川順子氏は述べており、その代表となるのが『ヘントの祭壇画』13の修復であるという。この作品の修復については、『神秘の子羊―調査と修復』というタイトルで詳細な報告書が作られ、その存在は日本の修理界にも大きな影響を与えている14。その報告書の作成にも大きな役割を果たしたコルマンスの修復に対する立場は、あくまで「芸術作品の感性的特質を重視する」というものであり、それは彼が所長を務めたベルギー王立文化財研究所の方針として捉えても良いと考える。王立研究所で行われた修復の内容については、ローマの中央修復研究所で行われていた方法と比較され、議論されることもあったという。ここから、ヨーロッパの中でも必ずしもすべての国がイタリアを中心に修復を行っていたというわけではないということがわかる。アルベール・フィリポの息子であり研究者であるポール・フィリポは、「美学的・博物学的関心から設定された美術館アイテムの保存修復を念頭においたブランディの立場に対する、慎重な抵抗と批判」15をもった考えを示している。
また、ベルギーの修復界の特徴として、「同部門に集まっていたスペイン、ノルウェー、ラテン・アメリカ、ポルトガル、オランダ、タイなど、さまざまな外国の修復訓練生が、各自の異なる教育を背景に、議論を戦わせた」という国際性が挙げられる。その中に日本から留学していた杉浦勉氏16が含まれていたことは、日本の修理界においても無関係ではないと考える。杉浦氏が留学先を決める際には、その直前にイタリア、ベルギー、フランス、イギリス、アメリカの関係機関を2か月かけて訪問して実際に様々な現場を目にしてきた岡行蔵氏17から、“壁画の修理ならイタリア、絵画の修理を学ぶならベルギー”と、ベルギー行きを薦められたということである。
「文化財研究所では作品に対して、歴史的あるいは科学的視点を含めて、さまざまな観点からの関心が寄せられていたが、それが何より芸術作品であるということを最も重んじたコルマンスの基本姿勢をアルベールは保ち続けた」18とある。そのような考えの下に指導が行われていた場所で学んでいた杉浦氏はその思想や姿勢に強く影響を受けたと考えられる。文章等の資料という形では残されてはいないものの、杉浦氏からベルギーにおける修復の考え方や技法についての情報が、日本にもたらされていた可能性はかなり高いと考えられる。実際、ベルギーで出版された報告書に影響を受けるような形で、調査や記録が行われ、修理報告書が作成されたという事実もある19。
日本の地色補彩もそこから影響を受けたという可能性や関係を期待したいところである。しかし森氏によると、ベルギーではイタリアのブランディの影響を受けた時期もあったが、補彩については基本的に“イリュージョニスチック”な方法が採られてきたということで、日本の地色補彩との関連を指摘するのは難しいのではないかということであった20。そして、渡邊明義氏も、特にヨーロッパの方針に影響を受けたということはない、という内容を生前話されていたということであった。
(第19回に続く)
《註》
1 田口かおり「美術作品修復における「中間色(Neutro)の可能性 チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に」『美学』62巻2号(239号)、美術出版社、2011年、p.62
2 田口かおり「美術作品修復における「中間色(Neutro)の可能性 チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に」『美学』62巻2号(239号)、美術出版社、2011年、p.62~63
3 アントネッロ・ダ・メッシーナの『受胎告知』は、1980年代と2007年(平成19年)から2008年(平成20年)、ローマ国立中央修復研究所により再度修復され、1940年(昭和15年)のブランディによる修復時とは異なる補彩が施されている。※2023年(令和5年)6月、田口かおり氏へのSNSでの質問に対するコメントによる。
4 田口かおり「美術作品修復における「中間色(Neutro)の可能性 チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に」『美学』62巻2号(239号)、美術出版社、2011年、p.63
5 バルディーニは、自らが考案した方法で、単色ではない中間色の色調を作り出し、さらなる中間色の可能性を試みたという。(田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.255)
6 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.102
7 田口かおり「修復における「中間色(Neutro)」の可能性-チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に-」『「美学会」発表要旨集』、2010年、p.121
8 田口かおり「美術作品修復における「中間色(Neutro)の可能性 チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に」『美学』62巻2号(239号)、美術出版社、2011年、p.62
9 田口かおり「修復における「中間色(Neutro)」の可能性-チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に-」『「美学会」発表要旨集』、2010年、p.121
10 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.102
11 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.101
12 森直義「残されている課題―ベルギーにおける絵画修復」『イタリアにおける美術作品の保存・修復の思想と歴史 欧米各国との比較から』(文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書)、2007年、p.107
13 『ヘントの祭壇画』は『神秘の子羊』と呼ばれることもある。
14 岡岩太郎「あとがき」(岡墨光堂 編『国宝 伝源頼朝像 国宝 伝平重盛像 国宝 伝藤原光能像 修理報告』岡岩太郎、1983)より
15 蜷川順子「ベルギーにおける芸術作品の保存・修復の思想と歴史-1950年《ヘントの祭壇画》修復の周辺とその後」『イタリアにおける美術作品の保存・修復の思想と歴史 欧米各国との比較から』(文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書)、2007年、p.170
16 杉浦勉氏はベルギーの王立文化財研究所に留学。絵画修復の理論と技術を学ぶと共に、ベルギーに日本の技術を伝えている。それが実際に応用された例もあるという。(蜷川順子「ベルギーにおける芸術作品の保存・修復の思想と歴史-1950年《ヘントの祭壇画》修復の周辺とその後」『イタリアにおける美術作品の保存・修復の思想と歴史 欧米各国との比較から』(文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書)、2007年、p.169)
昭和40年代には、岡墨光堂の本社工房にて藤田嗣治の戦争画の修理も行っており、当時墨光堂に在籍していた技術者と、作業内容や考え方等についての交流があった可能性は十分に考えられる。
17 「岡行蔵-明治43年(1910)3月9日京都市で生まれる。(略)昭和12年2代目岩太郎を襲名した。昭和22年頃から国宝、重要文化財などの国指定文化財を中心に古文化財の保存修理に従事、多くの名品の修復を手掛けて、昭和58年岩太郎の名跡を長男興造に譲るまで、工房全体の運営を監督していた。」(東文研アーカイブデータベースより)(2015年12月12日閲覧)
岡行蔵氏は当時としてはかなり革新的な考えを持った人物であったのではないかと考える。岡氏は1961年(昭和36年)に行われたIICローマ世界大会に参加、その後2か月近くをかけてイタリア、ベルギー、フランス、イギリス、アメリカの関係機関を見てまわる。その際、現地の技術者や研究者と言葉を交わす機会もあったであろうし、修復された作品を見る機会もあったであろう。実際、帰国後、岡氏はよく若い技術者達に「日本は修理に関しては未発達で、これから科学的な見地に基づいて修理をすすめるような方向がますます盛んとなる」という話をされていたという。そして「もたもたしていたら、全て(修理を)あちらに持っていかれる」という危機意識を常に持たれていたということであった。
18 蜷川順子「ベルギーにおける芸術作品の保存・修復の思想と歴史-1950年《ヘントの祭壇画》修復の周辺とその後」『イタリアにおける美術作品の保存・修復の思想と歴史 欧米各国との比較から』(文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書)、2007年、p.169
19 岡墨光堂 編『国宝 伝源頼朝像 国宝 伝平重盛像 国宝 伝藤原光能像 修理報告』岡岩太郎、1983 がそれにあたる。
20 森直義氏へのメールでの取材に対するコメントによる。