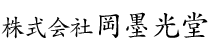2022年10月号:第14回 日本の文化財修理における“地色補彩”について(1)
亀井 亮子
○はじめに
絵画作品をなおす、修理1するということは、多くの工程を必要とする。“補彩”もその中の一つである。現在日本の絵画修理において“補彩”とよばれている作業の内容とは、画面の欠失部分に繕い補う絹や紙に直接色を入れるというものであり、補彩を施す箇所の絵画画面における位置や、占める割合によっては、修理後の作品の印象を決めることにもなる重要な工程である。そのため、作品に対して行われる補彩の方法に関する考え方とは、修理という行為において変化し得る絵画の総合的な見せ方と直結しており、絵画作品の修理後の芸術的な評価に影響を与える可能性さえも持ちうるものである。
現在、日本においては指定文化財の修理の中で補彩を行う際“地色補彩”という方法が基準であり、原則とされている。本論では、その“原則”が認識される以前に行われていた補彩とは全く異なるこの“地色補彩”がどのようにして行われ始めたのか、そして何故この方法が現在まで文化財絵画の補彩の“原則”として扱われるに至ったのかを検証することを目的とする。
検証材料の一つとして、イタリアで一時行われていた“中間色補彩”の成り立ちや技法が目的としたものを見ていくこととする。その上で“地色補彩”と“中間色補彩”という2種類の補彩方法を比較し、補彩という作業について再度見直してみると共に、日本で行われている文化財修理の補彩において、“地色補彩”とはどういうものであるのかということを改めて検証する。
日本国内での絵画の補彩に関する先行研究については、特に見あたらないため、補彩の方法を倫理的・哲学的な面から現場の技術者達と共に模索した渡邊明義氏の遺された文章と、当時実際に修理された作品の実例、そしてそれらの施工を行った工房の関係者へのインタビューなどを基に検証を進めることとする。
○第1章 絵をなおす―日本の絵画修理における“補彩”
第1節 文化財修理の方法としての補彩
日本において“補彩”という言葉は、美術史等の論文では使われていなかった。辞書類にも“補彩”という項目は無いが、現在、文化財修理業界では頻繁に使用されている。実はこの“補彩”という言葉がどこで作られていつから使われはじめたものなのか定かではない。日本で書かれた文化財修理に関連する書籍等で補彩についての解説を見てみると、「本紙の補修絹や補修紙を施した箇所に周囲の色調とバランスをとるために彩色を加える作業。本紙に描かれている作品に影響をおよぼすような線や彩色は施さずに地色を合わせる程度にとどめることが原則である」2と説明されている。また、他の書籍では「補絹をした箇所に、周囲との色調のバランスを取るための補彩を行う。本紙絹の余白部分の色調が基本なので、必ずしも、周囲の色と同じとは限らない。筆の線を濃淡で表現するなどは控える。以上が原則ではあるが、個々の作品の表現や現状を十分に検討し、それに合致したひかえ目な補彩が行われる」3と書かれている。使われている言葉は異なるが、どちらも同じような内容を説明しているといえる。しかし2つの文章の中にある“原則”とは、いつ頃から基本的な“原則”として認識されているのだろうか。それを知るためには、“補彩”という作業の歴史をたどっていく必要がある。補彩の方法、そしてその在り方自体に対する考えはどのように変わってきたのか、次節より日本国内における補彩についての具体的な変遷を検証していくこととする。
第2節 日本で行われていた“補彩”―明治以前
「江戸時代まで、いわゆる美術品を持っていたのは、将軍家や公家、大名・社寺などが中心であり、美術のコレクションは宗教・権力機構と強い関係を持っていた」4と、近代日本美術を研究する佐藤道信氏は述べている。更に加えてコレクションを築いた階層としては、その商いで富を蓄えた商人たちも含まれるであろう。しかし、彼らの築いたコレクションは、特に大衆に公開されることもなく、いわば小さいコミュニティーの中だけで礼拝され、また鑑賞されてきた。そしてそれらが修理される際にも、個々の職人への依頼をもって行われてきたであろうし、その行為に特に共通の決まり事などが存在したとは考えにくい。
そのような時代、明治以前の修理における補彩については、次のようなことが頻繁に行われていた。つまり「図が欠けているよりは備わっていた方がよく、色が脱落しているよりは明瞭であった方がよい。したがって色を加え、図を補うのである」5ということである。それ故に絵画作品には、今でも“文化財修理の原則が出来る以前に施された補彩”を見ることができるものが少なくない。例えば、京都国立博物館蔵の国宝『山水屏風』の修理された部分を見てみる。屏風の向かって右から2扇目、5・6扇目の大きい部分を占める補絹箇所には、山の稜線がうっすらと描かれていることが確認できる。また右から2扇目の上部中央や3扇目の右上の水の部分に繕われた後補の絹には、水を思わせる色が着けられている。これらはあきらかに絵の失われた部分を補おうとして行われた処置であろう6。
明治時代より以前に制作された絵画作品については、ほとんどの物に何らかの過去の修理の手が入っているといっても過言ではない。その目的としては、礼拝する対象とされたものであるなら、それ自体を何とか遺そうとしたということが考えられる。また別の目的としては、見た目を整え美しく見せる為に行われたものもあったに違いない。更には売買の際の値段をあげるためなど美術品の商品価値を上げるという理由で行われたこともあったであろう。いずれにしても、きれいに見せたい、遺したいという思いが連綿とそそがれることによって伝世品は遺されてきた。そして、大切なものを美しく伝えていきたいという思いにおいて、修理における補彩(この場合は補筆やオーバーペインティング7も含まれる)は、視覚的に有効な手段の一つであったといえる。
第3節 近代日本における文化財修理の概念の成立
明治の時代になり、文化的な面も含め様々なものが西洋の影響を大きく受け、美術という枠組みさえも根本的に変化していく中8、絵画の修理についても変化は例外ではなかったと考えられる。
1868年、明治という新しい時代を迎えた日本は、新政府の出した神仏分離令をきっかけに、廃仏毀釈の動きが激しくなり、伝統的なものを破却する風潮が激しくなっていく。仏像や神像は勿論、美術品や建造物にもその影響は及んでいく9。そこで、政府は“日本における最初の文化財保護制度”として1871年(明治4年)に「美術工芸品等31種類の古器旧物の保存方」を布告する。その後1897年(明治30年)には「古社寺保存法」を制定し、文化財の調査と保護を推進していく。
文化財修理に対する姿勢を明確にした最も早い例としては、1929年(昭和4年)に古社寺保存法に代わり制定された「国宝保存法」が挙げられる。ここにおいて「指定したときの現状を保存することを基準として(略)修理の際に行われる可能性のある恣意的な修理や、行き過ぎた修理などは、現状変更の制限規定によって現状維持の修理基準がもたらされる」10という方向が示された。国指定の文化財という存在に上記のルールが提示された時、それらの修理に対して倫理や哲学、統一した方針が必要となり、それら文化財の何をどう残すべきか、どのように見えるようにするべきかということが考えられ始めたのである。しかし、実はこの時点においては“文化財”という言葉は存在していなかった。「文化財という言葉がいつ頃誕生したのか定かではないが、文化財保護法の制定にかかわっていた文部省で、少なくとも1939年頃には使われていたらしい」と沢田正昭氏は述べている11。つまり、その頃から“文化財という概念”がはっきりと社会で認識されているということを沢田氏の言葉から推測することが出来るのである。
その後、公に“文化財”という言葉が使用されるのは、1950年(昭和25年)に施行される「文化財保護法」が最初となる。
(第15回に続く)
《註》
1 本論においては、修理と修復という言葉を同義であるとする。
2 東京藝術大学大学院文化財保存学日本画研究室編『日本画用語事典』東京美術、2007年、p.167
3 増田勝彦・尾立和則「装潢の技術」『在外日本美術の修復』中央公論社、1995年、p.170
4 佐藤道信『〈日本美術〉誕生 近代日本の「ことば」と戦略』講談社、1996年、p.206
5 渡辺明義「文化財の修理について-特に日本画の場合」『在外日本美術の修復』中央公論社、1995年、p.134
6 本作品は、1965年(昭和40年)に修理されているが、その当時既に復元的な修理は行わないということは周知され、厳守されていたと考えられる。そのため、補絹部分の加筆については、それ以前の旧修理跡と判断する。
7 ここでいうオーバーペインティングとは、欠失箇所を補ったところにのみ施されているはずの補彩(それによって塗布された絵具)が、本紙絵画上にまではみ出して塗られている状態を指す。
8 「日本で「美術」という語が初めて用いられたのは、前述のように明治六(一八七三)年のウィーン万博参加の際、出品をすすめる出品差出勤請書添付の出品規定においてだった。(略)ここでの「美術」は(略)音楽、絵画、彫刻、詩なども含んでおり、いまで言う芸術の意味に近い。しかしその原語は、ドイツ語のKunstgewerbeで、純粋芸術というより産業的な意味あいの強い”工芸美術“である。」(佐藤道信『〈日本美術〉誕生 近代日本の「ことば」と戦略』講談社、1996年、p34)
9 「古器旧物保存方の布告」
10 三輪嘉六・本田光子「文化財保存の道筋」『守り伝える日本の美 よみがえる国宝』九州国立博物館、2011年、p.12
11 沢田正昭「第一章 保存科学の歴史」『文化財のための保存科学入門』京都造形芸術大学編、角川書店、2002年、p.6