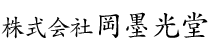2021年10月号:第12回 紙の分析
岡 興造(談)
○経験による判断から科学的判断へ
私たちの仕事で取り扱う紙には、美濃紙、美栖紙、宇陀紙など、表具に仕立てるときに裏側から使うものと、表紙(おもてがみ)という絵や書を描く/書くためのものがあります。私がこの世界に入った時分、昭和40年(1965)頃には、先輩達のなかに紙を持ってみるだけで「ああこれは何々です。いつの時代のものかな。」「これはだいぶ古いですね。」という具合に即座に言う人がいました。私は入ったばかりで何もわからず、先輩から仕事を聞くわけですから、紙がわかるというのはそういうものだと思っていましたし、すごい先輩達がたくさんいるんだなと思っていました。そのような「経験でものを見るのが優れた職人である」という時代に私のキャリアは始まったわけです。いつから私たちの世界で紙を科学的に見るようになったか振り返ってみると、昭和50年代後半のひとつの出会いがきっかけでした。そのお話をする前に、昭和50年代の状況を少しお話ししておきたいと思います。
○経済の活況と京都国立博物館文化財保存修理所の設立
昭和50年代は、私たち文化財修理の世界にとって変化の時期でした。昭和39年(1964)、東洋で初めての東京オリンピックが開催されて、日本の戦後にひとつ区切りがつき、昭和40年代には世の中が大きく変わっていきます。1ドル360円の固定相場制は、昭和48年(1973)から完全な変動相場制に移行し、経済が活況を呈しました。美術品についても、新画、古画にかかわらず金銭的価値が上がって盛んに流通し、表装関係の世界も忙しくなりました。
こうした世の中の動きにあわせて、修理事業に対する予算も大きく増加しました。そして、昭和55年(1980)に、京都国立博物館内に念願の文化財保存修理所ができたのです。昭和36年(1961)にIIC世界大会への参加とあわせて欧米の修復センターを歴訪していた父は、やっと修理所ができたと大いに喜んでいました。
文化財保存修理所の設立によって、社会的に修理の仕事が知られるようになります。一方で、昭和54(1979)年に奈良大学で日本初の文化財学科が創設されたように、大学の専門教育の中で文化財学が取り上げられるようになりました。社会的関心の高まりと、人材育成の仕組みができたことで、それまで人手不足であった技術者の応募が増え、その後現在に至るまで、男女を問わず、大学卒、大学院卒の人材が集まるようになりました。
○文化庁建造物課との材料調査
このように、日本全体の経済が活性化し、修理に対する社会的な認知が高まっていたのは、昭和50年代後半のことです。文化庁建造物課に委員会があり、指定文化財の建造物修理の材料について生産量や人材育成の状況を調査することになりました。当時、建造物に関する技術や材料は変化の時代にあって、例えば左官屋さんであれば、高齢の人や辞めたら後継となる若い人がいない、材料の土がないなど、技術の継承、材料の継承の両方でたくさんの課題がありました。私たち装潢師は、先程お話したように、技術継承の点ではあまり心配されていなかったのですが、襖や壁貼付などの修理で使う材料の紙が調査の対象になっていました。委員会には、国宝修理装潢師連盟から藤岡新三さんと私が派遣されました。本当は藤岡さんと父が出席するはずでしたが、父の体調の問題で私が代理で出席することになりました。今思えば、当時私は30代後半でキャリアは15年程でしたから、父は随分と大胆な判断をしたものだと思います。私にとっては初めての委員会出席でした。
委員会での着席は、五十音順でした。所属別でなく個人名での五十音順ですので、藤岡さんと並んで座るのではなく、私の隣は「おおかわ」さんという方でした。名刺を交換すると、大川(昭典)さんは高知県紙業試験場(現・高知県立紙産業技術センター)の方で、私の友人でもある画家の林功さんが共通の知り合いだとわかりました。林さんは東京芸術大学の保存修復技術の研究室にいて、昭和45年(1970)頃からよく私たちの工房に来ていました。林さんは、紙のことなら高知の紙業試験場がいろいろなことを知っていて作ってくれるということで、大川さんに相談したり、画家仲間で高知の紙を使ったりしていたそうです。
大川さんに、修理の現場には紙を触ってこれはいつの何だということを判定する人がいるという話をしたところ、紙というのは目で見ても材料はわからない、繊維を分析しないと判別は不可能だと言われます。ちょうど委員会に同席していた東京国立文化財研究所(現・独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所)の増田勝彦先生から「岡さん、その通りなんです。この文化財の世界には科学はまだまだ少数です。」と言われたことを思い出します。
○紙の生産現場で見たこと
委員会後、藤岡さんと私は、主に建造物の関連ということで障壁画に使用する紙を中心に、越前や美濃、石州など紙の生産地へ現地調査にまいりました。生産者が何人いて後継者がいる/いないなど、表を作って国に提出したことを覚えています。紙漉きの作業の一部はそれまでも見たことがありましたが、材料の準備から、各工程の作業、紙漉きをする人が現場でどういうことを見ているか、考えているかなど詳しいことは、そのとき初めて知りました。当時、美濃には人間国宝の古田行三さんがいらして、古田さんの話が面白く、昔の美濃はこうだったという話、紙漉きの技術の話、今の流通の話など、とにかくいろいろな話を聞きました。現地で見聞きするうちに、自分たちが使っている材料についてもっとしっかりみなければいけないと思うようになりました。紙漉きの技術は、地域によっても漉き手によっても個々に少しずつ技術や考え方が違うことがわかり、紙漉きの奥深さを知る機会となりました。
○ペーパーコンサべーションの常識
ちょうどその頃、よく交流のあった欧米の紙の修復家、ペーパーコンサべーションの人たちと会ったときに、日本から輸入している紙は木材パルプが入っていることがあるし、なかには酸性紙もあると言われました。驚いて「あなたたちは修復用の紙を分析してから使うのですか」と聞くと、「そうです。調べてからでないと、保存のために悪い結果を招いてはいけませんから」という答えです。海外の修復施設は商社から仕入れているので、紙自体のことを知るのはなかなか困難な時代でした。特にアメリカでは、科学的な裏付けを重視していて、鉄製の包丁や針は錆があるので、できれば使用しないという話までありました。
これは一度しっかり調べたほうがよいと思い、自分たちがそのとき扱っていた紙、全種類を大川さんに分析してもらうことにしました。結果として、原料のことがよくわかったほか、調べてもらった紙の中には木材パルプや再生紙が入っているものもあるということもわかりました。加えて、国産とばかり思っていた原料についても、これは国産ではありませんと言われるものがあり驚きました。使用している私たち自身がよく判断しなければならないということを強く思いました。しかしこれは、生産者が消費者をだましているということではありません。その頃の日本の伝統的な紙の条件が、例えば楮紙の場合、8割以上が楮であればそれが純楮紙であると定められていたのです。楮が国産かどうかは関係ありません。これを初めて知って驚いたのですが、昔からお付き合いをしている美濃ならばこの人、吉野ならばこの人という方々の漉いたものは、ちゃんと私たちが思っている通りの材料で作られていました。この結果を知って、なおのこと、これは現場に行ってちゃんとものを見ないといけないと痛感しました。このように、大川さんに相談し、現場を見て材料のことを考えないといけないと強く思うようになったのが、昭和50年代後半から60年代にかけての状況でした。先にお話したように、ちょうど京都国立博物館の文化財保存修理所ができて、この世界に自然科学の風が吹き始めたころのことです。
○本紙の分析
使用材料の分析が進むと、新たな疑問が生まれました。自分たちが修理している本紙は、分析なしに「楮です」「雁皮です」というふうに言われてきているけれど、果たしてそれは本当だろうかという問いです。そこで、大川さんの指導で、修理中の本紙の裏側の端のところから紙を指で触ったときに自然にとれてしまう程度の微量の繊維を採取して、分析を依頼してみました。このとき対象とした本紙は鎌倉時代の絵巻で、従来、楮と雁皮の混合紙だと考えられていたものです。それが分析をしてもらうと、楮100%であり、約10mmの繊維を3mm程度に切っていること、溜め漉きで漉いていること、切断された繊維がよく打たれているので、繊維の先がフィブリル化(箒状の毛羽立ち)し繊維同士がよく水素結合して紙ができあがっていること、できあがった紙を打つことによって表面を平らにしていることなど、初めて知ることとなりました。表面加工に驚いていると、大川さんが天平経を例に説明してくれました。天平経は楮100%で、繊維を本当に細かく切って、よく打って平らにしています。あの頃トロロアオイはなく流し漉きはないので溜め漉きです。漉いたあとは表面に凹凸があるので、よく打って平らにしなければなりません。平らにするとにじまなくなるのでサイジングも必要ないほどです。だから天平経というのは、表面を見ると墨が盛り上がって見えるほどになります。これが8,9世紀の紙なのだというお話です。それを知ってから紙の見方が変わり、さらに知りたいことが増えて面白くなってきました。分析結果が増え、記録が蓄積されていくと、どの時代のどういうものがあるか統計学的にものを見ることができるようになります。ただし、このとき、紙の分析に対する理解者はまだあまりおられず、裏側の繊維をごく微量採取することでも、それは文化財の破壊であるとお叱りを受けたことを思い出します。
本紙の分析で、ひとつ大きな出来事になったのが、正倉院宝物《鳥毛立女屛風》(正倉院所蔵)の修理です。修理は昭和60〜62年度に行われました。修理前に確認した参考文献には、鳥毛立女屛風の本紙は麻紙だと書いてありました。しかし、修理が始まり、大川さんに繊維の分析を依頼すると、楮という結果が出ました。詳しくは、大川さんの報告を参照してください(大川昭典「鳥毛立女屏風本紙繊維の調査について」『正倉院年報(現・正倉院紀要)』第12号、pp26-28、宮内庁正倉院事務所、1990年(https://shosoin.kunaicho.go.jp/api/bulletins/12/pdf/0000000152)。このような報告は、紙の繊維分析の結果が社会に出た例としてごく早いものだと思います。
このような経緯で本紙の繊維を知り、また紙加工についても調査をして、多くの記録をとってきました。特に弊社の創業100周年を機に『修復』という刊行物を出すようになってから、巻末に紙繊維の記録を残すようにしています。現代では繊維分析をし、記録することが当たり前になっていますが、先程少し触れたように初期は風当たりが大変強く、一技術者である私たちの行動が日の目を見るまでには時間がかかりました。
このような背景があるなかで、林功さんたちと新たに取り組んだのが復元模写事業です。それまで模写といえば、紙に描かれたものも絹に描かれたものも、すべて紙に現状をそのまま描き写すものでした。昭和50年(1975)頃に国宝《伝源頼朝像》(神護寺所蔵)の模写を行うとき、初めて絵絹を復元しました。糸の太さや織組織まで復元し、オリジナルにあわせて巾広の四尺巾の絹を京都の西陣で特別に注文して作ってもらい、その絵絹に模写を行ったのです。ちょうど、カラー写真が発達して、機械的な写真技術による記録ができるようになった時代です。それまでのように、伝統的な絵具を使用して記録のために現状を写し取るという模写から、考え方が大きく変化する時機でした。次に詳しくお話する、同技法同素材による復元模写の考え方は、このような時代背景のもと生まれたのです。
(第13回に続く)