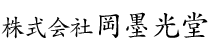2023年1月号:第17回 日本の文化財修理における“地色補彩“について(4)
亀井 亮子
○第3章 イタリアにおける文化財修復と補彩の歴史
第1節 欧米における“補彩”
日本で“補彩”と呼ばれているその工程は、英語では微妙なニュアンスの違いにより、現在いくつかの言葉が使い分けられているようである。
inpaintingはアメリカでよく使われる言葉だといい、以下のように定義されているという。「〈補彩inpainting〉とは、美術作品や文化遺産にみられる補填、補修、欠損箇所への適切な色材の付加を指す。その趣旨は、イメージと背景、もしくはいずれかの連続性を示すことにより、作品の全体像を想起させ、同時に欠損が引き起こす錯乱を最小限に抑えることである。そして、オリジナルの意図と材質を損なわずに、色材あるいは場合によっては支持体の欠損を補うことにより、視覚的な統一性を回復することを目的としている。」1それに対し、同じく補彩の対訳として使われることのあるretouchingには諸説あり、地域によっても扱いが異なるようである。その解説にあたる文章を見てみると「〈補彩retouching〉は国際的な用語であり、ヨーロッパ大陸やイギリス、スカンジナビア地方においては一般的なものである。(中略)数十年にわたり使用されている。(中略)〈補彩retouching〉という用語は、欠損部分や損傷個所における色調の補完は意味するが、補紙/補填の工程は含まない。保存修復専門家によって〈補彩retouching〉をオリジナルの支持体のみに対する色材の塗布と理解する者もいれば、補紙/補填部分への色材の塗布を示すためにこの語を用いる者もいる」2とある。どちらにしても、現在考える補彩についての意味を十分に満たしているが、近年は公式の報告書などでinpaintingの方がよく使われているようである。また、1995年(平成7年)に日本で出版された『在外日本美術の修復』3の対訳では、補彩を表す言葉としてtorningという表現が選ばれている。その他の国の事例として、イタリアでも過去にいくつかの言葉が使われたことがあったらしいが、現在の保存修復学の分野では、ritoccareという言葉が使われており、ベルギーではillusionnismeという言葉が“補彩”にあたるものだという。
以上のように、“補彩”を表す言葉は複数あり、対象となる作品も壁画であったり、テンペラ画や油絵であったりと様々であるが、現在では総じて絵画の欠失部分が補われた箇所に、何らかの形で色やそれに準ずるものを付加するという行為を表しているという点に変わりはない。
第2節 イタリア絵画修復史-補彩を中心に
修復の先進国の一つであるイタリアにおいて、“修復”と同義の処置は、方法はどうあれローマ時代から既に行われていた。しかし、それが近年のような意味を持つ言葉になるまでには、いくつかの段階を経なければならなかった。例えば、1900年代のある“贋作修復士”の活動を表す「「修復」と「複製」あるいは「加筆」「偽造」「制作」などが(中略)曖昧に重なり合っていた」4という言葉は、“修復”という言葉の意味が決して現在と同じではないということを如実に表している。“修復”の歴史が長いイタリアにおいても、近代的な意味をもつ“修復”の兆しは、17世紀になるまでみられなかった5。工房に所属する職人たちの手により特に共通した理念も無く様々な修復が行われていた時代、それぞれの職人の仕事内容については「質的にばらつきがあり、方針やしっかりとした教程に支えられたものではなかった」6とされる。しかしそれは決して悪いことでは無く、手仕事を生業とする職人の世界ではごく当たり前のことであった。そして、職人の中には偽物を作ることを堂々と公表していた者もいたようである7。
このような中、“補彩”を意味する言葉は14世紀後半には既に見られたというが、これも上記の“修復”と同様に現在と同じような意味ではなかった。ルネサンスの時代には、ヴァザーリが作品に対する補彩―現在で言う加筆、過去はこれも“補彩”の一種とされた―について批判したとの記録が遺されている8ことから、“補彩”についての大体の歴史や状況としては、イタリアも明治時代以前の日本とさほど変わりはなかったのではないだろうか。つまり「伝統的な西洋の補彩介入においては、欠損部分の空白をオリジナル部分との判別がつかないほどの精緻さで埋めることで、外観の統一的な美の回復を目指す例が多数見られた」9といわれるように、職人が絵の傷んだ箇所を見目良くするため、その技を駆使し、色を加え、形を加えて絵画の外観を整えていたのが“補彩”の初期の形態であるという点については、恐らくイタリアも日本も、そしてその他の地域においても大きな差は無いと考えられる。
やがて“修復”が近代的な兆候を示し始めるという17世紀を経て、18世紀になると専門的な技法書等も出版されるようになってはいくが、それぞれの技術者たちが独自に仕事をしていたという点ではあまり変わりは無かったようである。そして、18世紀末に画家が副業として修復を行う時代から脱却し、19世紀のはじめ頃には“保存修復”が独立した一分野として確立されていく。田口かおり氏は、その変化の背景には不可逆的介入への反省と強い危惧があったとしている。もしそうであれば、この動きは研究者のみから出たものではなく、技術者の中にもある種の危機感を感じていた者たちがいたのではないかと考えることはできないだろうか。
19世紀の半ばごろになると、2冊の「教育的な性質をもつ保存修復理論の本格的教本」が出版され、それを書いた2人の修復士はウフィッツィ美術館の公認修復士として採用されている10。以上のような歴史を経て、やがてイタリアは“修復”において「西洋他国を牽引するかたちで、技法的・思想的発展を遂げていく」11こととなるのである。その後、“修復”に共通したルールを定めるべきであると考える人々が主体となり、1938年(昭和13年)にローマの中央修復研究所の創設計画が起こる。そこで、具体的な方針として「新しい修復家の任務は、欠損部がオリジナルに見えるように(中略)上手にまねることではなく、本物の部分を見分けて尊重しながら(中略)作品の享受を保証するのに役立つもの以外には介入の手を加えるのを避けることである」12という考えが示されるのである。
そのような流れの延長線上にチェーザレ・ブランディが現れる。チェーザレ・ブランディは大学で哲学・歴史・法律を学び、その後芸術の世界へと足を踏み入れ、保存修復学の権威として影響力を持った人物である。
“修復”についての様々な思想が議論された中、1970年頃よりその方向性を定めたチェーザレ・ブランディは、以下の“修復”の3原則13を提唱する。
(1) 修復処置はあとで確認できるものでなければならない。
(2) 作品の構造に手を入れることはできるが、外観を変えてはいけない。
(3) 修復前の状態に戻すことができるように処置しなくてはならない。
これらは(文化も材料も異なるので、そっくりそのままというわけではないが)現在の日本においても、特に指定文化財の修理を行う際に踏まえておくべき原則として認識されているものである。田口氏はその著書で、イタリアの修復学はこれまでも「日本・諸外国へと伝統的な技法をもたらし、教育的な役割を果たしてきた」としつつ、チェーザレ・ブランディが現れた「結果、ブランディの介入技法と思想は、現在もなお、ある種の国際的なスタンダードとして活用されている」14と述べている。
では、具体的に“補彩”についてはどうだったのだろうか。イタリアにおいても“補彩”という言葉が現在のような意味で修復の用語として認知されるようになるのは近代以降であるという。現在に至るまで多くの国や研究者の間で激しいやり取りが繰り返されている“洗浄”に比べて、“補彩”についての議論が少ないと田口氏は述べている。「視覚的に明らかな方法であらたな素材を“付け足す”介入」とされる“補彩”は、当時目指された“最小限の介入”との矛盾という点で定義の困難が生まれ、それについて議論されるのが遅れたのだという15。しかし、可逆性のある材料や技法を使用するという方法を得て“補彩”という行為を考え、実際に目に見える形で様々なテストを行ったのが、前述したイタリアのチェーザレ・ブランディであった。
“補彩”の変遷は、「度々問題となった洗浄同様、時に作品の〈顔〉である彩色層を著しく変化させてきた」16とされ、その時々の技術のもたらす効果により、絵画の視覚的な印象やものによっては芸術的な価値さえも変えることとなってきたのである。そのような状況下で、それまでの伝統的な補彩とされる「欠損部分の空白をオリジナル部分との判別がつかないほどの精緻さで埋める」17補彩に対して、1940年頃から1970年代にかけて、チェーザレ・ブランディにより“中間色による補彩”が提唱された。その方法を構築するにあたって“ゲシュタルト心理学”を取り入れるなど、かなり理論に重きを置いた補彩方法であった。その方法を用いることで、オリジナルから視覚的に差異化をはかり、「偽証的な介入」を忌避しようと試みたのである。それがチェーザレ・ブランディによる“中間色の補彩”であった。
(第18回に続く)
《註》
1 ティナ・グレッテ・プールソン『修復は紡ぎだす詩』三好企画、2014年、p.20
2 ティナ・グレッテ・プールソン『修復は紡ぎだす詩』三好企画、2014年、p.20~23
3 平山郁夫編『在外日本美術の修復-絵画』中央公論社、1995年
4 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.84
5 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.10
6 ジュゼッペ・バジーレ「(日本語版序文)チェーザレ・ブランディについて」チェーザレ・ブランディ『修復の理論』三元社、2005年、p.13
7 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.78~86
8 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.76~77
9 田口かおり「修復における「中間色(Neutro)」の可能性-チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に-」『「美学会」発表要旨集』、2010年、p.121~122
10 「一八六六年、画家であり修復史であったウリッセ・フォルニによる『画家修復士の手引き(Manuale del pittore restauratore)』と、貴族階級に属し美術作品の蒐集家としても名を馳せた修復士ジョヴァンニ・セッコ・スアルドによる『絵画修復士が美術作品の構造部分を扱う際に有用な手引き(Manuale ragionato per la parte meccanica dell’arte del restauratore dei dipinti)』 が同時に発行された。」(田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.10より引用)
11 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.11
12 チェーザレ・ブランディ『修復の理論』三元社、2005年、p.13
13 森直義『修復からのメッセージ』ポーラ文化研究所、2003年、p.147
14 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.12
15・16 田口かおり「美術作品修復における「中間色(Neutro)の可能性 チェーザレ・ブランディおよび同時代の言説を中心に」『美学』62巻2号(239号)、美術出版社、2011年、p.64
17 田口かおり『保存修復の技法と思想』平凡社、2015年、p.75